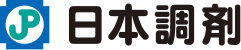-
日本調剤 最新機器「ドラッグステーション」導入による次世代の薬局運営に向けた調剤業務の効率化に関する実証実験開始~薬剤師の専門性や職能を患者さまへのきめ細かい対応に発揮するための基盤づくり~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、薬剤師の専門性や職能をより患者さまへのきめ細かい対応やサービスに発揮するための基盤づくりとして、2020年5月30日(予定)より「日本調剤 三田薬局」において、株式会社湯山製作所(本社所在地:大阪府豊中市、代表取締役:湯山 裕之)の最新機種である自動薬剤ピッキング装置「ドラッグステーション」を導入し、次世代の薬局運営に向けた調剤業務の効率化について実証実験を開始いたします。 厚生労働省の掲げる「患者のための薬局ビジョン」により、「対物業務から対人業務」への転換が進む中、当社ではかねてより、薬剤師本来の職能を発揮し、患者さまへのきめ細やかな服薬指導や、ご質問にお応えするため、また人為的な調剤過誤を防ぐため、薬局規模に適した調剤機器の選定及び活用による業務の効率化を推進してまいりました。 このたび当社では「ドラッグステーション」を導入し、今後の最新機器の導入による効率化によって変革が期待される薬局業務の実証実験を開始いたします。三田薬局の一部で行う実証実験では、調剤業務の効率化、調剤過誤や待ち時間の低減、店舗設計に至るまで、患者さまへの安全性・利便性の向上と、薬剤師の単純業務に係る負担軽減を検証する予定です。この実証実験を通じて得られた知見をもとに、複数店舗への当該機種の導入を視野に入れ、当社では薬剤師が専門性や職能をさらに発揮し、地域の患者さま、また地域包括ケアに向けたきめ細かい対応に注力できる次世代の薬局運営モデルの構築を加速します。 日本調剤では、超高齢社会の進展に伴い、調剤薬局のあり方が変化する中において、既存の枠組みに捉われない柔軟な発想をもって、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、新しい薬局事業モデルの創出に全力で注力してまいります。 ■株式会社湯山製作所 「ドラッグステーション」について 自動薬剤ピッキング装置「ドラッグステーション」は、薬剤師が単純作業にかける時間を低減し、患者さまに向き合う時間を創出することを目指し、本年8月に発売予定の機器となります。 株式会社湯山製作所の概要はこちらをご覧ください。(http://www.yuyama.co.jp/) ■三田薬局概要 店舗 : 日本調剤 三田薬局(https://www.nicho.co.jp/tenpo/mita/) 所在地 : 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビルアネックス1階 日本調剤 三田薬局内 導入機器 : 「ドラッグステーション」 【日本調剤株式会社について】 http://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp
-
日本調剤、ファルメディコと「FINDAT」に関する業務提携を開始 調剤薬局チェーン初*となる提携により、薬物治療の更なる質の向上を目指す
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、ファルメディコ株式会社(本社所在地:大阪府大阪市北区天神橋、代表取締役社長:狭間 研至、以下「ファルメディコ」)と、高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」の利活用に関する業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。 日本調剤では、超高齢化が進む中、欧米など先進国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じて安全で質の高い薬物治療の確立と、医療費削減に向けて両輪で取り組む中、2020年6月に「FINDAT」を開発し、医療機関における医薬品情報の標準化と効率化を支援してまいりました。2021年度からは、薬学部などの教育機関向けに「FINDAT」の提供を開始し、薬剤師教育にも注力しています。 ファルメディコでは、医療費適正化の観点から、介護が必要な高齢者の長期療養の場が医療機関から在宅・介護現場へシフトすることを見据え、早くから介護施設や在宅ケアなど、調剤や薬の配達にとどまらない地域医療制度を支える新しい薬局のあり方と、新しい薬剤師像を提唱・実践しています。 このたび、両社において「薬剤師が安全で質の高い薬物治療に注力できる環境を整え、地域医療に貢献していきたい」という想いが一致し、「FINDAT」の利活用に関する業務提携をする運びとなりました。この提携により、ファルメディコの7薬局における「FINDAT」の活用方法はじめ、「FINDAT」による医薬品情報収集の効率性や、処方提案における有用性などについて検証し、合同勉強会の中で意見交換を実施する予定です。 ファルメディコの代表取締役社長の狭間 研至氏は、「薬剤師の対人業務を推進し、安全で質の高い薬物治療を提供するためには、業務の効率化と良質な医薬品情報が必要です。今回在宅・介護現場を中心にFINDATを活用することで、患者さまにさらに質の高い薬物治療を提供するとともに、薬剤師が職能にさらに磨きをかけ対人業務に注力できるようになることを期待しています」とコメントしています。 また、日本調剤の取締役兼FINDAT事業部長の増原 慶壮は、「今回の提携により、在宅・介護現場におけるFINDATの活用事例を共有いただくことで、FINDATのコンテンツの拡充や各現場に応じた活用提案につなげていきます。また、薬剤師がチーム医療の中で職能を発揮し、患者さまにさらに質の高い薬物治療が提供できるよう支援を続けていきます」と述べています。 日本調剤では、高い専門性を持つ医療人材の担い手が職能を存分に発揮できる環境を整え、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、全力で注力してまいります。 *2021年8月25日現在 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【ファルメディコ株式会社について】 1976(昭和51)年に個人薬局として開局したハザマ薬局をもとに、医師でもある代表が2004(平成16)年に設立後、超高齢社会に求められる次世代型薬局として「薬局3.0」を提唱し、その具現化に取り組んでいます。要介護高齢者の在宅療養を支える薬局に取り組みながら、そこで得られた知見を、外来調剤業務、セルフメディケーションへと広げながら、医師と薬剤師がともに専門性を活かして地域医療の課題解決に取り組む「医薬協業」を目指して活動しています。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp ファルメディコ株式会社 総務部 TEL:06-4801-9555 FAX:06-4801-9556 E-Mail:soumu@pharmedico.com
-
「FINDAT」を日本調剤の薬局21店舗に展開 薬局店舗でのDI業務を強化し薬物治療のさらなる質の向上を目指す
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、4月より高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」を日本調剤が運営する全国の調剤薬局21店舗に先行導入したことをお知らせいたします。先行導入となる21店舗は各支店から1店舗以上を選出し、「FINDAT」の活用事例を検証、展開する拠点の役割を担います。当社では、「FINDAT」導入店舗の拡大を視野に、地域における医薬品情報室としての機能を強化し、薬物治療のさらなる質の向上を目指します。 当社では、ジェネリック医薬品の普及、有効活用を目指し、欧米など先進国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じた医療費の削減と標準薬物治療の推進に向けた様々な取り組みを行っています。その一つとして、2020年6月に「FINDAT」サービスを開始し、大学病院やDPC病院を中心とした医療機関における薬物治療の標準化と効率化を通じてDI業務の負担を軽減し、「対物業務から対人業務」への転換やチーム医療の充実、患者さまへの良質な医療サービスの提供を支援してまいりました。 このような中、2021年8月から施行される「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定制度において、地域の医療機関との薬物治療に関する情報提供の連携や、地域の医薬品情報室としての役割が施設基準として求められています。当社では、認定制度が目指す薬局の姿を体現し、患者さまに、より質の高い薬物治療を提供できるよう薬局店舗へ「FINDAT」を導入する運びとなりました。 先行導入店舗では、「FINDAT」を活用するための薬剤師教育に注力するとともに、トレーシングレポートや在宅訪問時における医師への処方提案などに活用するための手順を検証することで、患者さまが安心・安全に薬物治療を受けられる薬局運営を強化してまいります。 日本調剤では、社会や医療環境の変化に伴い、調剤薬局のあり方が変化する中において、高い専門性を持つ薬剤師が職能を存分に発揮できる環境を整え、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、新しい薬局事業モデルの創出に全力で注力してまいります。 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。
-
本邦初*の高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」サービスを開始 医薬品情報の標準化と業務の効率化を支援
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、医療機関における医薬品情報(DI:Drug Information)の収集・評価を一元管理することで、医薬品情報の標準化と効率化を支援する、本邦初*の"高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」"(https://www.findat.jp)を開発し、2020年6月1日よりリリースすることをお知らせいたします。 高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」は、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を、中立的に評価し、WEB上で配信するサービスです。「標準フォーミュラリー」、「薬効群比較レビュー」、「新薬評価」など、実務に役立つ医薬品情報の提供を通じて、医療機関における標準薬物治療を推進するための「フォーミュラリーマネジメント」や薬事委員会などの資料作成にお役立ていただけます。また、「FINDAT」をご利用いただくことで、原著論文の査読や新薬に関する情報収集など、DI業務に係る負担が軽減され、「対物業務から対人業務」への転換が求められる中、対人業務やチーム医療の充実が図れます。 日本調剤では、2019年4月に、「フォーミュラリー事業推進部」を創設し、企業理念でもある「真の医薬分業の実現」に向け、ジェネリック医薬品の普及、有効活用を目指し、欧米など先進諸国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じた医療費の削減と標準薬物治療の確立に取り組んできました。このたび、2020年6月1日より、「フォーミュラリー事業推進部」は「FINDAT事業部」に名称変更し、医薬品情報マネジメントに一層注力してまいります。 日本調剤では、当サービスの導入を通じて、超高齢社会の進展に伴い、調剤薬局のあり方が変化する中において、既存の枠組みに捉われない柔軟な発想をもって、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、新しい薬局事業モデルの創出に全力で注力してまいります。 *2020年5月25日時点、日本調剤調べ ■サービス概要 ・名称: FINDAT (呼称:ファインダット) ・形態: 医薬品情報のWEB配信サービス ・URL: https://www.findat.jp ・推奨閲覧端末: PC ・動作環境(ブラウザ): Google Chrome(最新版)、Microsoft Edge(最新版) ・提供開始日: 2020年6月1日(月) 12:00 ・提供施設: 医療機関(順次、調剤薬局、保険者等に拡大予定) ・料金: 1アカウント年間60万円(税別)※ ・契約方法: FINDAT (https://www.findat.jp)トップページのお問合せフォームより、ご連絡ください。 ※開始3か月はモニター病院に無料公開。本契約は9月以降。 ※医療機関ごとでのご契約となります。グループ病院等であっても、異なる医療機関でアカウントを共有することはできません。 ■病院モニター募集要領 ・受付期間: 2020年5月25日(月)~7月20日(月) ・モニター期間: 2020年6月1日(月)~8月31日(月) ・モニター条件: ・DI室を有する病院で、DI担当薬剤師が参加可能な施設 ・月1回のアンケートにご回答頂けること ・モニター申込み専用URL: https://forms.gle/nvHyBia6YAKVSnnF7 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT (https://www.findat.jp)トップページのお問合せフォームより、ご連絡ください。
-
日本調剤 「古河・猿島郡地域フォーミュラリー」作成に「FINDAT」を活用したコンサルティング業務を受託
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、ジェネリック医薬品の普及、有効活用を目指し、欧米など先進国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じた医療費の削減と標準薬物治療の推進に取り組んでいます。今回、当社では古河・猿島郡地域フォーミュラリー作成に関して「FINDAT」を活用したコンサルティング業務を受託いたしましたので、お知らせいたします。 ■古河・猿島郡地域フォーミュラリー 古河・猿島郡地域フォーミュラリーは、茨城県西部の古河・坂東医療圏にある中核3病院の、古河赤十字病院(古河市)、友愛記念病院(古河市)、茨城西南医療センター病院(境町)が共有する地域フォーミュラリーで、地域の薬物治療の標準化と薬剤費の節減を目指しています。 3病院で組織される幹部会と運営委員会にて、手順書や運用規定などの作成、薬効群の選定、地域フォーミュラリーの決定を経て、各病院で運用を開始し、運用後の評価も実施する予定です。また、地域勉強会などを通じて、このほかの医療機関へも共有していく予定です。 ■高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」を通じてのフォーミュラリー作成支援 日本調剤は2020年6月1日に、医療機関における標準薬物治療を推進するための「フォーミュラリーマネジメント」にお役立て頂ける、高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」(https://www.findat.jp)をリリースしました。 本コンサルティング業務では、高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」での医薬品情報提供や、フォーミュラリー作成・運用に関する研修会実施などを通じて、古河・猿島郡地域フォーミュラリーの作成を支援します。 日本調剤では、今後も継続可能な社会保障制度の基盤となる医療費適正化への取り組みを積極的に推進して、良質な医療サービスを提供する企業として社会に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。
-
日本調剤 東京医科歯科大学と共同研究を開始 DI業務における「FINDAT」の有用性の実証と機能充実化を目指す
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、国立大学法人東京医科歯科大学と、当社が提供する高度DI(医薬品情報)ウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」の有用性を実証する初めてとなる共同研究を開始いたしましたのでお知らせいたします。本研究では、東京医科歯科大学医学部附属病院におけるDI業務を通じて、「FINDAT」の有用性の実証と、既存コンテンツ「標準フォーミュラリー」及び「薬効群比較レビュー」の機能のさらなる充実化を目指します。 当社では、欧米など先進国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じた医療費の削減と標準薬物治療の確立に取り組む中、2020年6月から「FINDAT」サービスを開始し、医療機関における医薬品情報の収集・評価を一元管理することで医薬品情報の標準化と効率化を支援してまいりました。 このたび、東京医科歯科大学との共同研究において、東京医科歯科大学医学部附属病院の3つの対象薬「G-CSF製剤」「エリスロポエチン製剤」「速効型・超速効型インスリン製剤」の採用状況及び直近の年間使用実績を解析し、エビデンス収集と評価を行い、フォーミュラリーの応用について実証します。また、本研究を通じて、特定機能病院におけるバイオシミラーについての臨床的に重要な処方実態を踏まえ、「FINDAT」の既存コンテンツ「標準フォーミュラリー」及び「薬効群比較レビュー」の機能のさらなる充実を目指します。 ■東京医科歯科大学医学部附属病院との共同研究概要 ・研究開始日:2021年3月1日から2022年2月28日 ・研究題目:医薬品情報プラットフォーム「FINDAT」のDI業務における有用性実証及びその機能充実化に関する共同研究 ・研究目的:医薬品情報プラットフォーム「FINDAT」の特定機能病院における有用性とフォーミュラリーの応用について実証する。 ・研究内容:「G-CSF製剤」「エリスロポエチン製剤」「速効型・超速効型インスリン製剤」の採用状況及び直近の年間使用実績を解析。また、臨床的に重要な処方実態を踏まえて「標準フォーミュラリー」の応用について検証する。 日本調剤では、今後も継続可能な社会保障制度の基盤となる医療費適正化への取り組みを積極的に推進して、良質な医療サービスを提供する企業として地域社会に貢献してまいります。 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【FINDATに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。
-
【JPニュースレター】慶應義塾大学、日本調剤株式会社 共催セミナー「病院経営戦略における医薬品マネジメント ~フォーミュラリーの可能性と経営戦略~」
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、慶應義塾大学との共催セミナー「病院経営戦略における医薬品マネジメント~フォーミュラリーの可能性と経営戦略~」を5月21日に開催いたしました。 近年、病院経営を取り巻く環境が厳しさを増す中、医療機関にはコストを抑制しながら質の高い医療を提供するだけでなく、医療職の働き方改革の推進が求められています。本セミナーでは、病院経営における医薬品マネジメントと、それを後押しするフォーミュラリーに焦点を当て、各分野の第一人者の先生に病院経営、医療経済の観点からそれぞれご講演いただくとともに、当社取締役FINDAT事業部長 増原 慶壮からフォーミュラリーを支援する医薬品情報WEBプラットフォームFINDATについて発表いたしました。 また、ミニシンポジウム「病院経営における医薬品マネジメントの重要性」では、病院経営の効率化、安定化と持続可能な日本の社会保障制度に向けた医薬品マネジメントのあり方やフォーミュラリーの可能性について活発な意見交換が行われました。本ニュースレターでは、その一部をご紹介いたします。 ■当日のセミナー動画はこちら:https://info.findat.jp/newstopics/p1195/ ■病院経営の中で10-20%を占める薬剤費は、在庫管理、人材配置などを含め複合的な検討が必要 ミニシンポジウム冒頭、裵氏からの「病院経営の中で医薬品をどうとらえていくのか」という投げかけに対し、早くから独自の院内フォーミュラリーを導入している大坪氏は「DPC方式が導入された医療機関において、医薬品の公定価格と仕入れ価格との差分による薬価差益が少なくなる中、効果が同じであれば経済性を考慮したジェネリック医薬品を選択するなど薬剤費を抑えること、また欧米で普及しているフォーミュラリーを導入することが経営の安定化の一つの鍵になる」と述べられました。また、同院のフォーミュラリー作成をリードした当社増原によると、フォーミュラリーを導入することで、エビデンスに基づいた医薬品の整理が進み、結果、過剰在庫が抑えられ、在庫管理の手間の低減、業務の効率化にもつながることがわかっています。 ■これからの薬剤師は、エビデンスに基づいた処方提案と同様、エビデンスに基づいたコスト管理が必要 超高齢社会の進展により、2015年度以降概算医療費が40兆円*を超え続ける中、医療者自らが医薬品使用の適正化を進めることが期待されています。増原は聖マリアンナ医科大学病院在任中、採用薬の有効性・安全性のエビデンスを示すだけでなく、薬剤費の削減効果と病院収益に与える影響を数値化し、フォーミュラリー導入に向け必要な体制を構築した経験から、「理想論だけでは難しい。薬剤部長も経営者の一人なので、やりたいことを実現するためには、一つひとつのデータの積み重ねによる裏付けが必要」と述べました。これを受け裵氏は、「医療職は検査データに基づき患者さんを診断するのでデータ分析の素養がある。100億円の売上のある病院の薬剤部長は10億円の数字の責任を負っているので、病院経営の面でもその視点を応用してほしい」と今後の薬剤師への期待を述べられました。 ■病院経営における「バリューベース・プライシング」に基づいた価値の再定義が必要 近年欧米では、原価に利益を乗せて価格を設定するコストベース・プライシングだけではなく、付加価値から価格を設定するバリューベース・プライシングの考え方が導入されています。赤沢氏は、「医療経済評価の中でも高い、安いといった単純な価格評価だけではなく、患者満足度やPRO(Patient Reported Outcome)、さらには社会的影響を考慮することが必要になる」と強調しました。また、内視鏡手術支援ロボットを複数導入した海外の医療機関の事例を挙げ「業務効率だけで見れば不要かもしれないが、複数台導入したことで世界から注目される施設となり、優秀な研修医の誘致やレピュテーション向上に寄与したため、投資額以上のリターンがあった。病院経営全体の価値を再定義し、投資のメリハリをつけ、さらにそれらをエビデンスに基づいて評価できるようになることが理想」と述べられました。裵氏からも「経済的価値と非経済的価値の両面から中長期的な病院ブランディングを見据えた投資判断が必要になるだろう」との見解がありました。 ■院内フォーミュラリー導入に向けた経営層と現場の協働は医療従事者のタスクシェアにも寄与 2015年以降、厚生労働省が掲げる「患者のための薬局ビジョン」により、薬剤師業務の対物から対人中心への転換が推進され、2022年度の調剤報酬改定の中でも薬剤師の対人業務への評価が拡充されました。また、少子超高齢化による労働人口の減少を見据え、規制改革推進会議の中でも医療従事者のタスクシフト、タスクシェアが議論されています。このような中、大坪氏は、「当院ではフォーミュラリー導入に向けた体制構築に向けて、エビデンスに基づいた処方提案を行うための教育や薬剤師の病棟配置を行っていたため、薬剤師の対物から対人業務へのシフトは早くから実践されていた。対人の「人」は患者さんだけでなく医師や他の医療職も含まれるため、薬剤師が病棟で薬物治療にあたってくれることは医師にとっても大きな助けになる」と述べられました。また、フォーミュラリー導入に向けた成功要因については、「当初医師の反発もあったが、チーム医療を通じてコミュニケーションが増えることで良好な関係が構築できたこと、また病院の執行部がフォーミュラリー導入を強く支える意思表示をし、少しの反対意見では揺るがないものにすることも大切」と強調されました。 ■地域フォーミュラリーの導入に向けた3つのポイント 日本の医療政策において地域包括ケア、地域医療構想など、「地域」を中心とした軸での改革が進む中、裵氏から、「病院単体ではなく、地域という面で医療を捉えていく必要がある中、地域全体で共有する地域フォーミュラリーの果たす役割とは」という投げかけに対し、各氏から3つの示唆をいただきました。 最後に「日本の病院経営、地域医療は、予算制約の中で今後厳しさを増す。官民一体の改革、働き方改革、医療改革に加え、新型コロナウイルスのような外的要因も加わり、これまでの延長線上の考え方や、やり方では立ち行かなくなる中、私たちはフォーミュラリーという大きな武器を得た。医療の標準化、ひいては患者さんの笑顔のためにフォーミュラリーの展開を考えていきたい」と裵氏は締めくくりました。 日本調剤では、社会や医療環境の変化に伴い、調剤薬局・薬剤師の役割が多様化する中、DI業務の負担を軽減し医療従事者のタスクシェアを通じたチーム医療の充実、フォーミュラリーの作成をサポートし、患者さまの標準薬物治療の推進と持続可能な社会保障制度への貢献を目指します。 *厚生労働省 令和3年8月公表資料「令和2年度 医療費の動向」より引用 <FINDATについて> https://info.findat.jp/ FINDAT(ファインダット)は、医療従事者のための医薬品情報WEBプラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、WEB上でご提供するサービスです。 FINDATとは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※FINDATは日本調剤株式会社の登録商標です。 <日本調剤株式会社について> https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
お薬の専門家・薬剤師の役割
薬剤師ってどんな人? 病気の治療や健康維持に欠かせないお薬。その専門家として医療に携わっているのが薬剤師です。人の命にかかわるお薬を取り扱う重大な責任と、それを果たすための知識や技能、そしてなによりも医療人としての使命感が必要とされる職業です。 また、患者さまが不安に思っていること、ご本人が気づいていない問題点を見つけ出し、専門家の立場で解決にあたり、時には患者さまの声を代弁し、患者さま一人ひとりの治療や健康管理のお役に立つこと、それが薬剤師の本分なのです。 薬剤師の仕事薬剤師にしかできないこと 「お薬」は人の命や健康管理に直接かかわるもの。お薬を取り扱い、調剤し、患者さまにお渡しする業務は、本来、薬剤師にしかできない仕事です。豊富な専門知識はもちろん、業務に対する正確さと慎重さが求められます。 あらゆるお薬に対する専門家 医療用医薬品の数は約1万7千もあり、薬局へはさまざまな診療科目の処方箋が持ち込まれます。薬剤師はこれらに対応することができる“お薬のスペシャリスト”です。絶えず最新の医薬の知識・情報を吸収して、日々の業務にあたっています。 患者さまとのコミュニケーション お薬は、患者さまの不安を取り除き、安心して服用していただくことで、最大限に効果が発揮されます。そのためには、薬剤師には患者さまとのコミュニケーション能力が不可欠です。患者さま一人ひとりから信頼をいただき、お薬を適切に服用していただくかを考え、行動することは、薬剤師にとって最も重要なことです。 薬剤師になるには、薬学教育課程を有する大学(薬科大学や薬学部)を卒業後、薬剤師国家試験に合格しなければなりません。薬剤師養成のための薬学教育は以前4年制でしたが、現在では6年制となりました。これは医療技術が進み、医薬分業が定着するなか、高い資質を持った薬剤師の養成が求められているからです。 薬剤師になるには?ますます広がる薬剤師の仕事 薬剤師は、調剤薬局や病院以外にも、製薬メーカーや食品会社の研究員、MR(医療情報提供者)、医薬品の製造施設や医薬品管理施設等での管理薬剤師業務、行政機関や医薬教育の現場など、幅広い分野で活躍しています。超高齢社会において医療の重要性が高まるなか、薬剤師が必要とされる分野が広がっています。 日本調剤では、優秀な薬剤師を育てるため、数多くのカリキュラム、各種研修制度を設けて、薬剤師教育を実施しています。全国どこでも学べるe-ラーニングでの薬剤師養成カリキュラム、社内勉強会、社内イントラによる質疑応答システムなど、薬剤師の年次・経験にあわせて、さまざまな教育を行っています。日本調剤の薬剤師教育は、医療人としての高い意識をもち、日々進化する薬の知識を吸収し、社会に貢献する優秀な薬剤師の養成を目指して続けられています。 優秀な薬剤師を育てる
-
医薬品製造販売事業
日本調剤グループでは、日本全国に高品質なジェネリック医薬品を安定供給するべく、ジェネリック医薬品に特化した医薬品製造販売事業を行っています。日本全国に高品質のジェネリック医薬品をお届けするため、2005年に日本ジェネリックを設立し、日本調剤の薬局はもちろん全国の医療機関・薬局へジェネリック医薬品の安定供給を行っています。 2010年に茨城県つくば市の工場稼働を開始し、2012年から自社の研究所で開発し自社の工場で製造した製品の販売を開始するなど、開発から販売まで一貫した体制を整えています。日本調剤グループとしてのシナジーを生かし、患者さまや薬局現場の声を反映した製品を企画し、製造にあたっては、患者さまに安心してお使いいただけるよう、GMP※の厳格なルールのもと、教育されたスタッフが最新設備を用いて徹底した品質管理を行っています。 また、2013年には、豊富な事業経験と質の高い製造基盤を有する長生堂製薬が日本調剤グループに加入。現在では約500品目を超えるジェネリック医薬品を品揃えしており、日本の医療を支えるフルラインジェネリックメーカーを目指しています。 ※GMP(Good Manufacturing Practice):医薬品の製造管理及び品質管理の基準
-
薬剤師のお仕事を体験してみよう! 日本調剤、7月29日(土)開催の「職業体験EXPO2023」に初出展
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、7月29日(土)に開催される小中学生のための新しいカタチの職業体験イベント「職業体験EXPO 2023」(主催:職業体験EXPO実行委員会/株式会社バリューズフュージョン)に初出展することをお知らせいたします。 本イベントは「子どもと社会の出会い」をテーマに、全国の子どもたちに会社の取り組みや企業活動を学べる場を提供することで、社会のしくみを知ると同時に、将来の目標や職業感を育んでもらうことを目的としています。 日本調剤の出展ブースでは、『ドキドキ薬剤師体験!薬局の仕事を知ろう。』をテーマとし、薬局・薬剤師のお仕事内容やおくすり、病気の予防などについて楽しみながら学んでいただくために、クイズを交えながらレクチャーを行います。また、子どもたち自身にご家族の「かかりつけ薬剤師」となっていただき、調剤や服薬指導など、薬剤師の業務の一部を行っていただく体験コンテンツもご用意いたします。 ■職業体験 EXPO 2023 (リアル会場) 開催概要 【日 程】 2023 年 7 月 29 日(土) 11:00~17:00 【場 所】 住友不動産ベルサール渋谷ファースト (東京都渋谷区東 1 丁目 2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー B1) 【対 象】 小学 3~6 年生 【参加費】 無料。子どものみ要参加予約(同行者の事前予約は不要)となります。 ※子ども1名につき、同行者(大人)2名まで入場可能 【参加方法】 ①11:00 ②14:00の事前入場予約制(入れ替え制)となります。 以下、職業体験ドットコム内の職業体験 EXPO 公式サイトよりお申し込みください。 https://shokugyotaiken.com/event/200 【当社出展内容】 ・薬剤師やおくすりに関するクイズ・セミナー ・調剤・服薬指導など薬剤師の業務の一部を行う模擬体験 ※日本調剤はリアル会場のみに出展いたします 本イベント主催の株式会社バリューズフュージョンのプレスリリースはこちらからご覧いただけます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000043615.html 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤 従業員の「治療と仕事の両立支援」に取り組む企業として 東京都・神奈川県から認定 調剤薬局業界では初*
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、治療と仕事の両立について高い水準で取り組む企業として、厚生労働省が定める「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づき、東京都(2021年10月11日付)・神奈川県(2021年9月1日付)それぞれから認定を受けましたので、お知らせします。調剤薬局経営を主事業とする企業・業界では初めて*の取得となります。 《治療と仕事の両立支援とは》 病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として仕事の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組みです。 厚生労働省が作成した「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を元に各企業が環境整備を進めており、各自治体もセミナーや独自の認定制度でサポートしています。 《両立支援に係る当社の具体的な活動内容》 日本調剤でも、「会社を支える社員が安全に、健康な状態でいきいきと働くことができる職場」を目指し、従業員と組織の健康度を高める健康経営に取り組む中、治療と仕事の両立支援にも注力しています。 ○予防 ・乳がん、子宮がん検診等を含む生活習慣病項目に対し、定期健康診断費用を健康保険組合および会社から一部補助 (健康診断区分・年齢等によって自己負担額が異なります) ・健康診断受診に要する時間の就労免除 ○体制構築 ・統括産業医をはじめ精神科専門産業医/保健師/公認心理師の配置による社内相談窓口の強化 ・がん対策推進企業へ加盟登録 ○制度 ・私傷病で休職した際にも復職後安定的に業務に戻ることができるよう、段階的負荷(短縮勤務や業務量調整等)をかけていく復職プログラムの活用 《認定の概要》 ■東京都 東京労働局では、治療と仕事の両立支援を推進するため、取り組みを進めている企業の経営トップの基本方針を募集し、紹介しています。日本調剤でも、両立支援の環境整備に係る具体的な活動内容を含んだ基本方針を申請し、東京労働局のホームページで紹介されています。 詳しくは、東京労働局のホームページをご覧ください。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/newpage_00253.html ■神奈川県 神奈川県では神奈川産業保健総合支援センターと連携し、治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を整備している県内の企業を「かながわ治療と仕事の両立推進企業」として認定しています。日本調剤はこのたび、神奈川県の認定基準となる3つの項目全てを満たし、最高位である「プラチナ」の認定を受けました。 詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/chiryoutoshigoto.html 日本調剤では、今後も社会の変化をしっかり受け止め、多様かつ柔軟な働き方ができるよう、全社一体となり、社員・組織の健康度をさらに高める活動を推進していきます。 *2021年10月28日現在 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し3,000名超の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
明治薬科大学に教育機関向け初*となる「FINDAT」を提供開始 教育現場での「FINDAT」の活用を通じて薬物治療の実践スキル向上を支援
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、明治薬科大学に、2021年8月1日より高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」を提供開始したことをお知らせします。教育機関において「FINDAT」を導入いただくのは今回が初めてとなります。 当社では、欧米など先進国で普及しているフォーミュラリーの作成を通じて安全で質の高い薬物治療の確立と、医療費削減に向けて両輪で取り組む中、2020年6月から「FINDAT」を提供開始し、医療機関における医薬品情報の収集・評価を一元管理することで医薬品情報の標準化と効率化を支援してまいりました。「対物業務から対人業務」への転換やチーム医療の充実など、社会や医療環境の変化に伴い、薬剤師の専門性や職能をさらに発揮することが求められていることから、2021年度からは、薬学部などの教育機関への普及に向けた活動にも注力しています。 このたび、実践的なスキルを持った薬剤師の育成を通じて、患者さまへ安全で質の高い薬物治療を提供したいという想いに共感いただき、明治薬科大学においては「FINDAT」を導入し、EBM(Evidence Based Medicine)の視点に基づいて薬物選択を考える能力を養成することを目標とする薬物治療及び医薬品情報演習を担当する教員に活用して頂くことになりました。薬剤師として最適な薬物治療を支えるために、「FINDAT」の活用を通じて、情報の信頼性や科学的根拠を評価するための基礎的な知識や、欧米などの先進国で普及しているフォーミュラリーの作成手順、最新の医薬品情報を効率よく収集し臨床や研究に応用するためのスキルなど、薬物治療の担い手として実践的な知識の修得を支援します。 日本調剤では、高い専門性を持つ医療人材の担い手が職能を存分に発揮できる環境を整え、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、全力で注力してまいります。 *2021年8月2日現在 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp
-
最先端のICTを生かす
日本調剤は、医療サービスの品質向上のため、積極的にICTを活用しています。最先端の技術を生かす日本調剤の取り組みをご紹介します。医療の安全・安心を確保して、社会貢献 日本調剤では、創業当初からIT(情報技術)の持つ特性に着目し、積極的にコンピューターシステムやネットワークを取り入れ、いち早く調剤業務のIT化を進めてきました。今では全国のすべての薬局店舗が本社と基幹ネットワークで結ばれており、各店舗の状況をリアルタイムで把握できるオペレーションを行っています。 長年培ってきたナレッジやノウハウをICT(Information and Communication Technology)として最大限活用することにより、日本調剤が提供する医療サービスの質をさらに高めるという好循環を生み出しています。 システム専門部署を設置して迅速に対応 日本調剤では自社内に情報システム専門部署を置き、医療制度の変更、行政からの指示事項、医薬品の発売や安全性情報など調剤薬局運営に必要な情報を収集し、迅速に対応できる体制をとっています。最新の機能を盛り込み、処方箋の受付から調剤、鑑査、窓口での服薬指導まで、あらゆる業務がデータ化・蓄積されており、調剤薬局業務に必要となるさまざまなシステムで活用されています。 コンプライアンスを重視した自社開発の調剤システム 医薬品の調剤は人的要素が必ず介在する業務であるため、自社開発した調剤システム内には、ヒューマンエラーを限りなく減らすためのプログラムが多数織り込まれています。個人情報である処方情報も暗号化し、厳重なセキュリティ体制を敷いています。 また、業界ではいち早く生体静脈認証システムを採用し、なりすましを未然に防ぐことで調剤業務の透明性を確保するなど、コンプライアンス(法令順守)を重視した調剤システムを構築しており、日々、調剤業務の改善に取り組んでいます。 患者さま目線で利便性を高めた「お薬手帳プラス」 日本調剤では2014年から自社開発の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」の運用を開始しています。患者さまの調剤情報がスマホアプリに自動連携されることで、患者さまの服薬情報をいつでも身近に管理していただけます。また、血圧や血糖値、歩数などの日々の健康記録や薬局への処方箋情報の送信などにも対応しており、患者さまの利便性やニーズを重視したサービスの提供を心がけています。 ご自宅で服薬指導を受けられる「日本調剤 オンライン薬局サービス NiCOMS」 日本調剤では2020年9月より「日本調剤 オンライン薬局サービス NiCOMS」の運用を開始しています。自社開発の調剤システムに登録された患者さま情報に連動しているため、患者さまは簡単にご利用を開始できます。予約機能・ビデオ通話機能を備えた本サービスを通じ、いつでもどこにいても患者さまに安心して治療・服薬を継続いただけるようサポートします。 ※画像はイメージです 日本調剤では、現在地から、診療科からなど、さまざまな項目から医療機関を検索できるサイト、オンライン診療検索「NiCOナビ」も運営しています。本サービスを利用すれば、患者さまはオンライン診療に対応する医療機関とオンライン服薬指導に対応する薬局をまとめて選択することができます。 オンライン診療検索「NiCOナビ」医療機関のオンライン化をサポート 日本調剤では、患者さまが自宅で簡単に診療・服薬指導を受けられるスマート医療の実現を目指し、オンライン服薬指導の普及拡大に向けた活動を行っております。また、「オンライン診療の導入を検討されている」「導入後に課題を抱えている」医療機関・団体のサポートを行っております。 最新の調剤機器導入で調剤ミスゼロへ 患者さまの生命・健康を守る調剤薬局の業務において、調剤ミスはあってはならないものという意識を持ち、可能な限りゼロに近づけることが責務です。日々の業務での調剤ミス防止策や、定期的な社内勉強会開催などの意識喚起はもちろん、調剤システム上でのヒューマンエラー防止策のほか、全自動錠剤散薬分包機、一包化鑑査システムなどの最新鋭の調剤機器を積極的に導入し、ICTを最大限活用した複合的に調剤ミスを防止する取り組みを行っています。 情報分析で医療環境を改善 現在、日本調剤の薬局で受け取る処方箋枚数は年間1,700万枚以上。そこから派生する莫大な調剤レセプト情報を管理するだけでなく、膨大な処方情報から厳正に個人情報を取り除いたうえで、データを分析・解析しています。業務改善や業績分析、薬剤師教育などの社内活用はもちろん、分析調査や医薬品に関する動向研究など、医療環境の改善に役立つ有益な医療の分析情報として、グループ会社である株式会社日本医薬総合研究所を通じて、製薬メーカーや医療関係団体などへの提供・コンサルティングを実施しています。 これらは、医薬品の開発や疾患啓発活動への反映など、患者さまの医療環境に改善をもたらす情報として活用されています。
-
Social 社会への取り組み
日本調剤の社会への取り組みの一部をご紹介します。店舗における盲ろうの方々への支援情報の周知の取り組み 当社では持続可能な社会づくりのために「難病や障害などの医療福祉領域への支援」をマテリアリティに掲げ、医療機関としての社会的責任を果たすべく取り組みを進めております。 筑波大学附属視覚特別支援学校と連携し日本調剤の700店舗以上*で独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が発行する冊子「盲ろう児への支援を啓蒙・啓発するリーフレット」をご来局者さま向けに配付しました。国立特別支援教育総合研究所は特別支援教育の振興を図る機関で、視覚と聴覚の両方に障害のある「盲ろう」の子どもたちの教育に必要な情報提供や、盲ろうのお子さんを持つ保護者への交流機会の提供などを行っています。盲ろうの子どもを持つ家庭には、受けられる支援に関する情報が十分に行き届いていないなどの課題があります。店舗でこのリーフレットを配布することで、教育を必要とする盲ろうの子どもたちに支援が届く一助となるよう啓発活動を進めました。 また400店舗*で「盲ろう医療サポート 医療関連施設ご案内窓口開設のお知らせ」ポスターを掲示しました。このポスターは盲ろうの方々とその医療に関わる方々向けに、盲ろうの方々が必要なサポートを受けられる医療関連施設のご案内窓口やそれらの情報を検索できるウェブサイトを周知するものです。これらは独立行政法人国立病院機構 東京医療センターなどが中心となり開設したもので、ウェブサイト(「視覚聴覚二重障害の医療~盲ろう医療支援情報ネット~」)では、その他にも盲ろうの方々が受けられる各種支援内容や医療者関係者向けに診察に必要な情報も検索することが可能です。 当社では今後も、難病や障害などをお持ちの方々への支援に向けて取り組みを進めていきます。 *実施店舗数はいずれも2023年1月20日時点新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全国の当社薬局における電話やオンラインによる服薬指導、お薬の配送を実施 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困難になる中、厚生労働省より2020年4月10日に発出された通知により、薬局における電話やビデオ通話などによる情報通信機器を用いた服薬指導と、お薬の配送が時限的・特例的に可能となる措置がとられました。当社では、FAX等を用いた処方箋の受付、電話等による服薬指導、お薬の配送を実施しました。株式会社MICINのオンライン診療サービス「curon(クロン)」を通じて医療機関と処方箋をFAXで共有できる体制を構築しています。また、一部薬局では、ビデオ通話を通じた服薬指導を実施するため、株式会社メドレーの調剤窓口支援システム「Pharms(ファームス)」を導入して対応しています。 また、2020年11月より株式会社フルタイムシステムと共同で、非接触での処方薬の受け渡しについての実証実験を開始し、実証実験終了後も複数の薬局で活用しています。非対面の受け渡しサービスを活用することで、患者さまは薬局の営業時間外であっても、いつでも非接触かつ安全に処方薬を受け取ることが可能となり、新型コロナウイルスの感染拡大による感染リスクの低減、利便性の向上が期待できます。 国が提携する新型コロナウイルス感染症拡大防止策紹介サイトに、 当社電子お薬手帳「お薬手帳プラス」の活用事例が紹介されました 経済産業省、農林水産省、消費者庁と公益財団法人流通経済研究所が連携して開設した新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組み事例を紹介するサイト(https://distribute-dei-taisaku.jp/)に、当社の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」を活用した迅速なお薬の受け渡しなどの複数の取り組みが、薬局の好事例として紹介されました。当社薬局では、患者さまの薬局内での待ち時間を最小限に抑えるために、「お薬手帳プラス」の「処方箋送信機能」を活用し、事前に処方箋を薬局へ送信していただくことで、迅速にお薬の受け渡しができるよう努めています。その他、下記の取り組みを本社・支店・薬局で行うことで、患者さまの感染予防と、薬局で働く従業員の感染予防にも配慮した体制を整えました。 日々の健康づくりをサポート!健康チェックステーション 2016年度より日本調剤の薬局内に、「健康チェックステーション」を積極的に開設しています。「健康チェックステーション」では、地域住民の皆さまの未病・予防への各種取り組みを行っています。さまざまな健康イベントやお薬相談会を開催することに加え、主要な店舗では管理栄養士を中心に栄養相談を行うなど、生活面も含めた地域住民の皆さまの健康づくりのお手伝いをしています。 詳細はこちらをご覧ください。 認定栄養ケア・ステーション 2024年6月1日時点で、日本調剤の薬局18店舗が「認定栄養ケア・ステーション」の拠点として認定されています。 「認定栄養ケア・ステーション」とは、管理栄養士・栄養士が栄養ケアを行う地域密着型の拠点として日本栄養士会の認定を受けた事業所です。管理栄養士・栄養士が、地域住民の皆さまの食に寄り添い、栄養ケアの支援と指導を通じて生涯にわたる実りある豊かで健やかな生活維持が可能な地域社会づくりを目指すものです。医療機関と連携した食事療法や通院が困難な方への訪問栄養相談を実施する他、自治体、健康保険組合、民間企業、医療機関などを対象に料理教室の運営や献立考案、特定保健指導をはじめとした栄養関連サービスの提供なども行い、多面的に地域の健康づくりを支援します。医療機関や介護施設等との連携をさらに強化して地域住民の健康増進や介護予防により一層注力していきます。 詳細はこちらをご覧ください。 憧れの薬剤師さんのお仕事にチャレンジ!子ども薬剤師体験 毎年、大好評の「子ども薬剤師体験」を実施しています。本イベントは、薬剤師体験を通して、お薬を安全に飲むことの重要性や、薬剤師がどのように地域住民の健康維持に貢献しているのかを伝える活動として継続しています。 学会発表は17学会で41演題を発表 2023年度は、17学会に参加し41演題を発表しました。当社ではオンライン服薬指導を展開しており、日本遠隔医療学会では「オンライン服薬指導・オンライン診療に関する意識調査と処方傾向について」などの発表や分科会への参加を行いました。 双葉薬局での東日本大震災対応 東日本大震災当時、日本調剤では、被災地域の皆さまに対する服薬情報の提供活動を行いました。薬局の営業休止中に患者さまに対してお電話での相談窓口を設け、お薬の服薬情報を提供しました。 また、震災から1カ月を過ぎたころに、避難指定区域内の「日本調剤 双葉薬局(福島県双葉町:現在は閉局)」では、双葉町避難所(埼玉県加須市)において、当社薬局を利用された患者さまの「お薬相談コーナー」を開設し、情報提供を積極的に行いました。 各地で避難されていた当社薬局を利用された患者さまや、避難先で患者さまが受診される医療機関からはお問い合わせが多くあり、日本調剤の本社に保管されている患者さまのバックアップデータを使って対応しました。患者さまからは「飲んでいた薬が分からず不安だった」「震災前に自分が服用していた薬の情報を知ることができ安心した」との声が寄せられました。 責任ある調達・公正な取引の推進 当社グループでは、お取引先と責任ある調達や健全な協力体制を構築し、公正な取引を推進するために、調達に関する基本方針を定めるとともに、お取引先ホットラインを設置しております。 詳細はこちらからご覧いただけます。
-
薬剤師による新型コロナワクチン集団接種への協力スタート 日本調剤 新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、新型コロナワクチンの集団接種の拡大に伴い、ワクチン接種業務における薬剤師としてのサポートを加速させています。これまで日本調剤では、ワクチン接種協力に向けた準備を進めてきましたが、このほど全国の各自治体、薬剤師会をはじめとした各関係団体からの要請に基づき、日本全国で進められている新型コロナワクチンの集団接種運営へ協力しています。医療従事者である薬剤師が多数在籍する日本調剤から、23都道府県で行われるワクチン接種に延べ604名の当社薬剤師が加わっております(2021年6月8日現在。予定も含む)。 当社では患者さまはもちろん、地域住民や関係先等の皆さま、従業員の安心・安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に積極的に取り組んでまいりました。 全国的にワクチンの集団接種が進んでいく中、ワクチン接種の担い手である医療従事者不足などの課題が顕在化しています。各自治体では、迅速かつ正確にワクチン接種を進めるための体制づくりを進めており、各地域の新型コロナワクチン接種推進部署から当社薬剤師への協力要請をいただいている状況です。 当社では、ワクチン集団接種の円滑な実施に向け薬剤師の能力を生かした業務を行うために、ワクチン接種(手技)の講習会への参加、社内研修会の実施などを事前に行ってきました。薬剤師の知識と経験を生かして、今回、各自治体への協力を開始しております。今後、新型コロナウイルスの早期収束に向けて、ワクチン接種のさらなる規模拡大、実施の迅速化に対しても積極的にサポートしていく予定です。 当社はこれまでも、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、オンライン服薬指導サービスをはじめとした非接触サービスの拡充や、薬局店舗での社会的PCR検査の導入などを進めてきました。今後は、全国各地で行われる集団接種への協力を広げていくことで、一層、地域医療と社会への貢献を果たしてまいります。 【新型コロナウイルスワクチン集団接種協力の概要について】 ※いずれも2021年6月8日時点 ・協力実施地域:23都道府県 北海道、秋田県、山形県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、愛知県、三重県、岐阜県、大阪府、兵庫県、石川県、岡山県、島根県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、宮崎県 ・協力薬剤師数:延べ604名 ・主な協力業務: 集団接種会場での予診サポート業務、新型コロナワクチンの希釈業務*¹・充填業務*²、接種後の状況観察業務、医薬品の管理業務、接種前後の相談対応業務 *1 ワクチンの原液を生理食塩水で薄める業務 *2 ワクチンを規定量、注射器に注入する業務 【当社薬局の新型コロナウイルス感染拡大防止へ取り組み】 ・オンライン服薬指導を受けられる「日本調剤 オンライン薬局サービス」の利用推進 関連リリース:https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20200901_nr2/ ・バイク便による即日配送や宅配ボックスを活用した非接触の医薬品受取サービスの導入 関連リリース:https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20210107_nr1/ https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20201210_nr1/ ・薬局で受けられる社会的PCR検査の導入 関連リリース:https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20210601_nr2/ ※当社薬局店舗での対応:https://www.nicho.co.jp/pharmacy/covid19/ 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤 松阪薬局、三重県大台町での医療・行政MaaS*の実証実験においてオンライン服薬指導で協力
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省が連携して選定する令和4年度スマートシティ関連事業のうち、経済産業省「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(地域新MaaS*創出推進事業)」としてMRT株式会社(本社所在地:東京都渋谷区、以下「MRT」)などが主体となり2022年10月6日から11月末まで実施する「令和4年度 医療・行政MaaS」の実証実験において、日本調剤 松阪薬局(三重県松阪市)がオンライン服薬指導の分野で協力することをお知らせします。本実証実験では、車両内での医療サービスと行政サービスの提供の他、公的施設の活用や薬剤の配送との連携による取り組みの有効性を検証します。日本調剤 松阪薬局は10月6日から10月20日の期間のうち2日間、オンライン服薬指導実施薬局の一つとして本事業に協力いたします。 *MaaS(マース/Mobility as a Service):複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適な組み合わせで統合し、移動の利便性向上や地域の課題解決に貢献する仕組み https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/ MRTなどが主体となり実施する本実証実験では、さまざまな用途に利用可能なマルチタスク車両を活用して、車両内で医療サービスと行政サービスを提供する他、公的施設の活用や薬剤の配送との連携による取り組みの有効性を検証します。具体的には、三重県大台町の報徳診療所および近隣の薬局が協力し、町内の集会場などを巡回するマルチタスク車両を用いて、オンライン診療からオンライン服薬指導、さらには薬剤の配送までの一気通貫の流れを検証します。また、車両内ではマイナンバーカードの申請などの行政に関するオンライン手続きも行います。 また、日本調剤 松阪薬局は、オンライン服薬指導実施薬局の一つとして本実証実験に協力し、日本調剤が開発したオンライン服薬指導システム「日本調剤オンライン薬局サービス NiCOMS」を活用します。 ■「令和4年度 医療・行政MaaS」の実証実験について MRTなどが主体となり実施する本実証実験では、マルチタスク車両が地域住民の社会基盤(インフラ)としての役割を担う存在になるよう、「医療・行政・交通」の視点で医療MaaSの社会実装に向けた検証を行い、過疎化や高齢化などが進む地域の医療・交通関連の課題解決を目指します。 日本調剤では、本実証実験の参画を通じて患者さまの利便性向上と良質な医療サービスの提供を目指し、地域医療に貢献してまいります。 <実証実験概要> ・実施場所 : 三重県大台町 ・協力医療機関 : 大台町報徳診療所 ・協力薬局 : 日本調剤 松阪薬局 (https://www.nicho.co.jp/tenpo/matuzaka/) 勝栄堂薬局 ・実施内容 : [医療]オンライン診療・オンライン服薬指導 [行政]マイナンバーカードの申請・その他行政手続き [交通]通院困難者のサポート ・実施期間 : 10月6日~11月末 <サービス概念図> 出典:MRT他事業体より発出されたプレスリリース https://medrt.co.jp/pr/pdf/news-2022-1006.pdf ■日本調剤 オンライン薬局サービス「NiCOMS」について NiCOMSは、オンライン服薬指導が実施可能となった2020年9月1日に合わせて自社開発した、無料でご利用いただけるオンライン服薬指導システムです。予約機能、ビデオ通話機能、お支払い機能を備え、全国の日本調剤の薬局で運用しています。 NiCOMS公式サイト:https://nicoms.nicho.co.jp/ ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤、ドローンによる離島への医薬品配送の飛行実験に参画 ~非対面方式による一気通貫のオンライン診療実現に向けた体制を構築~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、愛知県の「無人飛行ロボット社会実装推進事業」の一環として名鉄グループドローン共同事業体(代表者:名古屋鉄道株式会社、構成員:中日本航空株式会社)が実施する、JA愛知厚生連知多厚生病院(以下「知多厚生病院」)が取り組むオンライン診療・オンライン服薬指導と連動した、無人飛行ロボット「ドローン」を利用した「離島への医薬品輸送」に関する飛行実験に参画いたします。 愛知県では、内閣府の未来技術社会実装事業である「『産業首都あいち』が生み出す近未来技術集積・社会実装プロジェクト」の一つとして、2019年度から「無人飛行ロボット社会実装推進事業」を行っています。日本調剤では、患者さまにあまねく良質な医療サービスを提供するため、2019年に知多厚生病院と連携し、離島における遠隔服薬指導の実証実験を重ね、非対面方式による一気通貫のオンライン診療・オンライン服薬指導の体制を構築してまいりました。 本飛行実験では、2020年11月11日及び、11月12日(※報道機関向け公開実験日は11月12日)の二日間にわたり、知多厚生病院が篠島(南知多町)で取り組んでいるオンライン診療・オンライン服薬指導事業の課題の一つである患者さまへの医薬品配送に対して、無人飛行ロボットを活用した際の、医薬品輸送における温度管理等の安全性、配送スピード、運用コストなどの検証を目的に、離島におけるオンライン診療・オンライン服薬指導から医薬品配送までを一気通貫して非対面式で行う流れを実証します。 日本調剤では、本飛行実験への参画を通じてさらなる地域医療への貢献と、システム開発のノウハウを生かして患者さまの利便性向上につなげることで、良質な医療サービスを提供し、社会に貢献してまいります。 *画像提供:株式会社プロドローン ◆実証実験概要 1. 報道機関向け公開実験日 2020年11月12日(木) 午前9時30分から 2. 実証地域 愛知県知多郡美浜町、南知多町 3. 飛行ルート 美浜町河和港から南知多町篠島北部(ゴルフ場跡地)の全長約14km 4. 実験内容 ・美浜町の港から篠島までの約14kmの洋上を飛行ルートに設定し、LTE通信を使用した飛行レベル3(無人地域での補助者無し目視外飛行)で医薬品を輸送 ・ヘリコプターと無人飛行ロボットの運航管理システムを連携し、互いの位置情報を監視できるシステムにより飛行ルートの空域管理を検証 ・医師、薬局薬剤師のよるオンライン診療・オンライン服薬指導を想定したデモンストレーション、医薬品配送後の着荷確認を通じた非対面による一連の流れの実証 5. 事業実施体制 事業主体: 愛知県 実施事業者: 名鉄グループドローン共同事業体(代表者:名古屋鉄道株式会社、構成員:中日本航空株式会社) 協力事業者: 日本調剤株式会社(オンライン服薬指導) JA愛知厚生連知多厚生病院(オンライン診療) 株式会社プロドローン(機体管理) KDDI株式会社(通信監理) 協力自治体: 美浜町 南知多町 ◆運用モデルイメージ ◆運航管理システムの連接イメージ ◆実施場所 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。
-
日本調剤の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」の会員数が100万人を突破! 抽選で100名様に賞品が当たる記念キャンペーンを開催
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)が2014年に自社開発し、全国の日本調剤グループの薬局で運用を続けてきた電子お薬手帳「お薬手帳プラス」の登録会員が、100万人を突破いたしましたのでお知らせします。(2022年2月16日現在の総会員数)これを記念し、本日2月16日より「『お薬手帳プラス』会員100万人突破記念キャンペーン」を実施いたします。 ■「お薬手帳プラス」会員数100万人突破記念キャンペーンについて 〈キャンペーン概要〉 このたび2022年2月に日本調剤の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」の会員数が100万人を突破いたしました。これを記念し、抽選で100名に賞品が当たる「『お薬手帳プラス』会員数100万人突破記念キャンペーン」を実施いたします。 キャンペーン応募期間: 2022年2月16日(水)9:00~2022年3月1日(火)23:59 賞品名: 「健康を考えた もち麦粥」(3種類×3食入り)1箱 当選者数: 100名さま 当選者発表: 厳正なる抽選の上、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 ※賞品の発送は2022年4月頃を予定しています。 キャンペーンページURL: https://portal.okusuriplus.com/2022/02/16/4265/ ※キャンペーンページ内の注意事項をご確認のうえご応募ください ■日本調剤の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」について 「お薬手帳プラス」は紙のお薬手帳の情報をスマートフォン上で管理できることに加え、日々の健康管理に役立つ安心・便利な機能が充実したアプリです。お薬の受け渡しまでの待ち時間を有効活用できる「処方せん送信機能」の他に、日々の健康管理に便利な体重・血圧・血糖値などを数値・グラフで記録できる「健康記録機能」や、病院や薬局の通院記録などの登録やお薬の服用時間にアラームでお知らせができる「カレンダー 飲み忘れチェック記録機能」など充実した機能をそろえています。また、日本調剤の薬局でお渡ししたお薬については、来局ごとのお薬情報が自動登録されます*。登録した1台のスマートフォンでご家族のお薬情報をまとめて管理できる「家族管理」設定も可能*です。 * 日本調剤の薬局をご利用の本会員限定の機能です ■「お薬手帳プラス」サポートサイト https://portal.okusuriplus.com/ 「お薬手帳プラス」の機能詳細は、こちらでご覧いただけます。 日本調剤の薬局へお越しの際には「お薬手帳プラス」の「処方せん送信」機能を通じて、薬局へ処方箋情報をお送りいただくと、お薬の準備ができ次第アプリでお知らせいたしますので、薬局でお待ちいただく時間を最小限に抑えることができます。新型コロナウイルス感染拡大防止の一助として、薬局ご利用の患者さまにご活用いただいています。 日本調剤では、今後も患者さまが安心して治療・服薬を継続できるよう「お薬手帳プラス」を活用して一人ひとりの健康をサポートし、医療と社会に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤、「外来がん治療認定薬剤師」認定者が21名に ―薬局所属認定者の約4分の1を占める人数―
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)では、患者さまに質の高い医療を提供するため、薬剤師の専門性を高める様々な取り組みを行なっております。その一つとして、日本臨床腫瘍薬学会(以下「JASPO」)が定める「外来がん治療認定薬剤師」の取得推進を進めており、2020年4月末時点の認定者が21名となったことをご報告いたします。これは調剤薬局業界の中でトップの人数であり、薬局に所属する認定薬剤師のうち約4人に1人が日本調剤グループの薬剤師※であることを示します。 厚生労働省が掲げる「患者のための薬局ビジョン」により、「対物業務から対人業務」への転換が進む中、高度薬学管理への対応が求められています。日本調剤は創業当初から”医療人”としての薬剤師教育に注力しており、質の高い薬剤師を育成する多彩な教育制度を展開しています。教育専任スタッフを中心にきめ細やかなフォロー体制を構築し、基礎・専門共に一人ひとりに合わせたスキルアップをサポートしています。 その中で近年特に当社が注力しているのが、がん治療に対応できる薬剤師の育成です。現在のがん治療は外来が主流になりつつあり、院外でも安心して薬物治療を続けられるよう、高度なスキルと専門知識を持った薬局薬剤師が必要とされています。その専門性を有した薬剤師の指標の一つとなるのが、JASPO「外来がん治療認定薬剤師」です。認定取得には試験のほか、3年以上の実務経験や治療サポートの事例報告などが必要で、薬局所属の認定者は全国でわずか85名※です。 日本調剤では将来的に認定薬剤師100名の養成を目指し、様々な資格取得の支援を行なっています。取得希望者を集めた強化チームを結成し、資格取得に必要な症例報告のサポートや、申請にかかる費用の補助などの仕組みを整えています。また、2019年度からは薬剤師のさらなるモチベーション向上とスキルアップを後押しするため、外来がん治療認定薬剤師を含む特定の外部認定資格を持つ社員に対し、一定額の手当を支給する人事制度を導入しています。 当社では、高い専門性を持つ薬剤師が職能を存分に発揮できる環境を整えることで、地域医療に貢献してまいります。 ※「外来がん治療認定薬剤師名簿 2020年4月末現在」より当社にて集計 以上 【JASPO「外来がん治療認定薬剤師」制度について】 外来がん治療を安全に行うための知識とスキルを持ち、がん患者さまとそのご家族をサポートできる薬剤師を養成するために創設された制度です。 詳細についてはJASPOの公式サイトをご参照ください。 https://jaspo-oncology.org/apacc/
-
日本調剤、紀伊國屋書店と「FINDAT」の教育機関向け販売代理店契約締結 「FINDAT」の教育現場への活用を通じて学生の実践スキル向上を支援
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、株式会社紀伊國屋書店(代表取締役会長兼社長:高井 昌史、以下「紀伊國屋書店」)と、高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」の教育機関向けの販売について、販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。 「FINDAT」は、医療機関における医薬品情報の収集・評価を一元管理することで、医薬品情報の標準化と効率化を支援する高度DIウェブプラットフォームです。これまで大学病院やDPC病院を中心とした医療機関に導入いただき、患者さまへの良質な医療サービスの提供を支援してまいりました。 「対物業務から対人業務」への転換やチーム医療の充実など、社会や医療環境の変化に伴い、薬剤師が専門性や職能をさらに発揮することが求められています。薬剤師として最適な薬物治療を支えるために、医薬品情報の収集に加え、情報の信頼性や科学的根拠を評価するための基礎的な知識や、主体的な提案能力がますます求められるようになっています。また、社会要請に伴い、薬剤師国家試験の出題範囲も変化し、実践的なスキルが求められるようになっています。 このような中、当社では、実践的なスキルを持った薬剤師の育成支援を目指し、全国の教育機関に強いパイプをもつ紀伊國屋書店と「FINDAT」に関する販売契約を締結しました。「FINDAT」の活用を通じて、最適な薬物治療を選択する思考プロセスや、欧米などの先進国で普及しているフォーミュラリーの作成手順、最新の医薬品情報を効率よく収集し臨床や研究に応用するためのスキルなど、薬物治療の担い手として実践的な知識の修得を支援します。 日本調剤では、高い専門性を持つ医療人材の担い手が職能を存分に発揮できる環境を整え、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために、全力で注力してまいります。 ■教育機関向けサービス概要 ・名称: FINDAT (呼称:ファインダット) ・URL: https://www.findat.jp ・推奨閲覧端末: PC ・動作環境(ブラウザ): Google Chrome(最新版)、Microsoft Edge(最新版) ・提供施設: 医療系大学(薬学部・医学部等) ・料金: アカデミックプランをご用意しております。詳しくはお問い合わせください ・契約方法: 紀伊國屋書店との契約締結後、FINDATの利用申込書を記載いただきます ・認証方式:ID/パスワード 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【株式会社紀伊國屋書店について】 昭和2年(1927年)に創業し、90年以上の歴史を持つ日本最大規模の書店チェーンです。外商部門は現在「営業総本部」として、北海道から沖縄まで日本全国に展開する28の営業拠点と海外6営業所3事務所、専門部署5本部を擁します。全国の大学・企業及び中学・高校へ、国内外の書籍・雑誌・データベース・電子書籍の販売から、教育研究設備・備品の納入、図書館業務の受託まで、幅広いサービスを提供しています。学術雑誌市場においても3,000を超える出版社・学会等と取引を行っており、日本の学術研究の発展に貢献しています。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp 株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL:03-5719-2501 FAX:03-5436-6921 E-Mail:ict_ebook@kinokuniya.co.jp
-
日本調剤、オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」での処方薬の「対面受け取り」へ全国店舗※1で対応開始 ~受け取り方法に自宅配送以外の新たな選択肢を追加~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、株式会社メドレー(本社:東京都港区六本木、代表取締役社長:瀧口 浩平、以下「メドレー」)が提供するかかりつけ薬局支援システム「Pharms」(以下、「Pharms」)での、処方薬の対面受け取りのためのネット受付の予約機能に対応します。これにより、12月1日より当社が展開する全国の調剤薬局※1にて、患者さまはメドレーが提供するオンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」(以下、「CLINICS」)を通じて、処方薬の対面受け取りのための予約が可能になります。 ※1 一部の薬局は除く ■オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」上で選択した日本調剤の薬局で、処方薬の受け取りが可能に オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」は、インターネットを通じて、自宅や職場からいつもの医師との診察、薬剤師との服薬指導を受けることができるサービスです。診察料・調剤料などはクレジットカードでの決済が可能です。「CLINICS」を利用することで、通院時間や待合室での待ち時間を削減できるため、忙しい患者さまでも治療を続けられるメリットがあり、またオンライン服薬指導を受ければ処方薬も自宅などへ配送されるので受け取りに行く手間も省け、通院による二次感染の防止にもつながります。 これまで「CLINICS」に登録された日本調剤の薬局では、処方薬の受け取りは配送に限られていましたが、このたび処方箋送信申し込み時に選択した薬局での処方薬の「対面受け取り」への対応を開始することとなりました。これにより処方薬の配送料は不要となるほか、最短で診療当日に処方薬を受け取ることが可能となります。今後もメドレーとともにオンライン診療・オンライン服薬指導のさらなる推進・普及を目指し、患者さまにとってより利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。 オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS」の概要やご利用方法の詳細は、下記よりご覧ください。 オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS(クリニクス)」 https://clinics.medley.life ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。 【株式会社メドレーについて】 https://www.medley.jp/ メドレーは、エンジニアと医師・医療従事者を含む開発チームを有し、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、インターネットサービスを提供しています。現在、より良い医療・介護の実現に向けて、以下のサービスを展開しています。 患者向け「オンライン診療・服薬指導アプリ CLINICS」 診療所・病院向け「クラウド診療支援システムCLINICS」 調剤薬局窓口支援システム「Pharms」 クラウド歯科業務支援システム「Dentis」 医師たちがつくるオンライン医療事典「MEDLEY」 医療介護福祉の人材採用システム「ジョブメドレー」 オンライン動画研修サービス「ジョブメドレーアカデミー」 医療につよい介護施設・老人ホームの検索サイト「介護のほんね」 退院調整業務支援サービス「れんけーさん」
-
医療用医薬品の仕入、購入について
お客さま各位 平素は日本調剤をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 さて、先般より報道されておりますC型肝炎治療薬の偽造医薬品問題について、偽造された医薬品は、製薬メーカーとの正規取引関係にない卸売業者から仕入れたものとされております。 当社では、製薬メーカーと正規取引関係にない卸売業者からの医療用医薬品の仕入・購入は一切ございません。従いまして、当社薬局では偽造品を交付することはございませんのでご安心ください。 今後ともご愛顧いただけますようよろしくお願い申し上げます。 平成29年2月7日 日本調剤株式会社
-
日本調剤 松阪薬局、三重県大台町での医療・行政MaaS*の実証実験 昨年に引き続きオンライン服薬指導で協力
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省が連携して選定する令和5年度スマートシティ関連事業のうち、経済産業省「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(地域新MaaS創出推進事業)」の実証事業としてMRT株式会社(本社所在地:東京都渋谷区、以下「MRT」)などが主体となり、2023年10月27日から2024年1月末まで実施する「令和5年度 医療・行政MaaS」の実証実験において、昨年に引き続き日本調剤 松阪薬局(三重県松阪市)がオンライン服薬指導の分野で協力することをお知らせします。 本実証実験では、車両内での医療サービスと行政サービスの提供の他、公的施設の活用や薬剤の配送との連携による取り組みの有効性を検証します。日本調剤 松阪薬局は実施期間のうち、11月2日から2024年1月末までの間、オンライン服薬指導実施薬局の一つとして本事業に協力いたします。 *MaaS(マース/Mobility as a Service):複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適な組み合わせで統合し、移動の利便性向上や地域の課題解決に貢献する仕組み https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/ ■「令和5年度 医療MaaS(中山間地域における住民の健康・生活を維持するモビリティサービス実装事業)」の実証実験について MRTなどが主体となり実施する本実証実験地域は、中山間地域のため利便性の高い公共交通手段が十分に供給されておらず、多くの住民は生活圏での移動を自家用車に大きく依存せざるを得ない状況です。このような中、運転免許証を返納する高齢者が増加しており、通院や買い物など生活に不可欠な活動が制限されてしまいます。このような中山間地域において、住民の健康と生活を支える利便性の高いモビリティサービスは必要不可欠です。 本実証実験では、「医療MaaSの省人化・効率化」及び「車両を活用した中山間地での地域拠点形成」による公共交通の負担軽減や地域の賑わい等に新たな効果を見出だせるかを検証します。また、実装を見据え、さまざまな用途や需要に適した車両を選択します。 具体的には、「医療MaaSの省人化・効率化(医療MaaSのさらなる深化)」については、過年度の実証実験の評価等を踏まえ、三重県大台町や近隣地域(自治体)をフィールドに、小型乗用車の活用や機器の高度化、医師間連携の視点で検証します。また、「車両を活用した中山間地での地域拠点形成」については三重県度会町をフィールドに、中山間地近くの公共施設等を地域拠点とし、現状中心市街地まで走らせている公共交通機関の代替えとして、買い物、医療など生活に必要なサービスを集め、地域拠点までの移動をサポートすることで、地域の賑わいの創造と公共交通の再構築の可能性を検証します。 また、日本調剤 松阪薬局は、オンライン服薬指導実施薬局の一つとして本実証実験に協力します。昨年の実証実験の評価等を踏まえ、医療MaaS対応スタッフの運用負荷を下げより円滑に進められるよう、診療所との相互連携を強化するほか、患者さまのご了承のもと事前にオンライン服薬指導時の問診内容や服薬情報の確認等を診療所と行い、服薬指導の対応品質の向上も目指します。 MRTなどが主体となり実施する本実証実験では、これらの新たなモビリティサービスが地域住民の社会基盤(インフラ)としての役割を担うサービスになるよう、過疎化や高齢化などが進む地域の医療・生活・交通関連の地域課題の解決につながり、かつ持続可能な施策の社会実装を目指します。 日本調剤では、本実証実験の参画を通じて患者さまの利便性向上と良質な医療サービスの提供を目指し、地域医療に貢献してまいります。 <実証実験概要> ・実施場所 : 三重県大台町、三重県度会町、他 ・協力医療機関: 大台町報徳診療所、越智ファミリークリニック ・協力薬局 : 日本調剤 松阪薬局 (https://www.nicho.co.jp/tenpo/matuzaka/) ・実施内容 : [医療]オンライン診療、オンライン服薬指導 [生活」地域拠点での買い物サービス、行政サービス等の提供 [交通]日常移動のサポート ・実施期間 : 2023年10月27日~2024年1月末 <連携イメージ> <サービス概念図> ■移動サービス×医療(医療MaaSのさらなる深化) 出典:MRT他事業体より発出されたプレスリリース https://medrt.co.jp/pr/pdf/news-2023-1027.pdf ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤、ドローン・地上配送ロボット連携による個宅配送実証実験に協力 ~都市部におけるドローン等宅配サービスの実現を目指して~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、国土交通省の実証事業「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」の一環として、株式会社ダイヤサービス(本社:千葉県千葉市花見川区、代表取締役社長:戸出 智祐、以下「ダイヤサービス」)を実施主体とした共同企業体が実施する、千葉市におけるドローンと地上配送ロボットが連携して医薬品をマンション個宅まで運ぶ実証実験の実施に協力いたします。 千葉市では、配達時間の短縮等による利便性の向上や、物流業界が抱える人手不足、ラストワンマ イルの問題、配送コストの削減等の課題解決を目的として、都市部におけるドローン等を活用した宅配 サービスの実現を目指し、2016 年から各種実証実験を行っています。千葉市のドローン宅配構想として、 東京湾臨海部の物流倉庫から幕張新都心まで東京湾上空飛行を行い、海上から花見川を遡上し、若 葉住宅地区のマンション個宅の玄関前まで配送を行うことを目指しています。 本実証実験では、幕張ベイパーククロスタワー&レジデンス(マンション内外)および若葉3丁目公園にて、ドローンをマンション付近まで飛行させ、積載した荷物をドローンポートを介して地上配送ロボットへ受け渡し、エレベーターを経てマンション個宅の玄関前まで配送する実験を行います。 *画像・イメージ図提供:ダイヤサービス ◆実証実験概要 1.報道機関向け公開実験日 2023年12月20日(水) 12:00~13:30 (予備日 2023年12月22日(金)) 2.実証場所 幕張ベイパーククロスタワー&レジデンス(マンション内外)および若葉3丁目公園 3.ドローンの飛行ルートおよび地上配送ロボットの走行ルート *画像提供:千葉市 4.配送物 医薬品(解熱剤、咳止め・痰切り混合剤) ※実証では模擬の医薬品を使用します。 5.取材について ドローンの離着陸の様子や、ドローンポートおよび地上配送ロボットとの連携などを公開します(マンション屋内への立ち入りは不可)。なお、当日は市長が視察(12:30~13:30)の予定です。 取材希望の方は、12月15日(金)17:00までに千葉市国家戦略特区推進課へのお申し込みが必要となります。詳細は、千葉市公開のプレスリリースよりご確認ください。 千葉市プレスリリース https://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/231205-1-1.pdf 取材申込用紙 https://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/231205-1-2.pdf 6.事業実施体制 7.「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」(国土交通省)の概要 過疎地域等における課題を解決するため、レベル4飛行に対応したドローン物流やドローンの離発着前後の配送を担う自動配送ロボット等と連携した物流等を社会実装する際に必要となる事項を検証することを目的とした先導的な実証事業をいいます。 日本調剤では、本実証実験への協力を通じてさらなる地域医療への貢献と、誰もが安心して治療・服薬を継続できる体制を整備し、地域の皆さまの健康に貢献してまいります。 ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤、新たに在宅支援センター5拠点でISO9001を取得 安全で高品質な在宅医療サービスを強化
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、自宅や施設で治療を行う患者さま向けの調剤をはじめとした在宅医療業務を行う「在宅支援センター」において、新たに5拠点で国際認証規格 ISO9001の認証を取得したことをお知らせします。これにより全国27拠点ある在宅支援センターのうち26拠点での取得が完了し、残る1拠点でも取得を進めます。 ISO9001は国際標準化機構が定める、製品及びサービスの品質を継続的に向上させるための品質マネジメントシステム規格であり、取得拠点ではより高い安全性と正確性の担保が期待できます。在宅支援センターでは他の医療従事者や介護従事者と連携しながら、高齢の患者さまのみならず、がん等の重篤な疾患や難病をお持ちの小児の患者さまへ薬物治療を提供しています。最新の調剤機器導入により調剤業務を効率化することで、服薬指導をはじめとした対人業務の充実に努めているのが特徴です。 2021年4月に2拠点で初めてISO9001を取得して以来、在宅支援センターでは品質マネジメントシステムの構築とパフォーマンス評価を通じて、一層の医療安全の確保に努めてきました。今後も確かな安全性と一体となった在宅医療業務を拡大していくことで、地域の医療インフラとしての機能を高めてまいります。 【新たにISO9001認証取得した在宅支援センター】 ※いずれも2022年10月25日付 ・日本調剤 盛岡本宮薬局(岩手県盛岡市) https://www.nicho.co.jp/tenpo/moriokamotomiya/ ・日本調剤 取手中央薬局(茨城県取手市) https://www.nicho.co.jp/tenpo/toridechuo/ ・日本調剤 北本東口薬局(埼玉県北本市) https://www.nicho.co.jp/tenpo/kitamotohigashiguchi/ ・日本調剤 静岡豊田薬局(静岡県静岡市) https://www.nicho.co.jp/tenpo/shizuokatoyoda/ ・日本調剤 湊川薬局(兵庫県神戸市) https://www.nicho.co.jp/tenpo/minatogawa/ 【在宅支援センターについて】 超高齢化社会の進展を背景として年々ニーズの高まる在宅医療に特化した当社独自の薬局のこと。在宅医療の経験豊富な薬剤師を配置して、医師の診察への同行・配薬・服薬指導のほか、臨時薬等に柔軟に対応するなど、地域のニーズに合わせて在宅医療を提供する拠点。 ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
在宅医療における迅速な連携をサポート<在宅コミュニケーションシステム構築>
全都道府県で調剤薬局チェーンを展開している日本調剤株式会社(代表取締役社長:三津原博、本社:東京都千代田区、東証1部)は、在宅で療養される患者さまへの在宅薬剤提供業務(以降、在宅業務)において、多機能情報端末である「iPad」を活用して、同業務を正確かつ迅速に行い、かつ在宅医療チーム間での連携が図れる「日本調剤・在宅コミュニケーションシステム」を構築、本格運用を開始しています。 ●日本調剤の在宅業務への取り組み 国内での超高齢社会の到来により、医療機関での入院による治療から自宅で治療を継続していく"在宅療養"への移行が進められております。その中で、地域医療における調剤薬局の役割が増しています。創業以来「医薬分業」を企業理念として掲げ、調剤薬局を全国展開している日本調剤では、調剤薬局における在宅業務への貢献を重視して、昨年度より在宅専門部門を設けて、積極的な取り組みを開始しました。 ●在宅医療現場におけるIT活用サポート 処方せんの受付から、調剤、服薬指導、お薬のお渡しまですべて薬局内で完結する調剤薬局業務とは異なり、在宅業務では患者さまのご自宅での服薬指導や報告事項の記録など、在宅業務では移動先での作業が重要になってまいります。業務遂行にあたり課題となってくるのが、移動先での情報管理。在宅医療現場においては、処方情報などの患者さまの重要な個人情報の厳格な管理が求められています。また患者さまの療養計画をサポートする在宅医療チームでの患者さまに関する情報の迅速な伝達、共有化も重要となっています。 日本調剤では、こうした在宅療養や高齢者介護施設での薬剤提供業務に取り組むにあたり、多機能情報端末「iPad」の機能を最大限活用して、医療としての必要要件を満たした、独自の在宅医療におけるコミュニケーションシステムを、医療系のシステム構築で知られる株式会社メディエイドの開発協力を受け、独自に構築、全国で展開する日本調剤の調剤薬局店舗で運用を開始しました。 ●「日本調剤・在宅コミュニケーションシステム」の主な特長 在宅現場での利用を前提とした本システムには、次の特長があります。 1.移動先での業務効率化サポート 軽量で携帯性に優れたiPad採用により、患者さまや応需施設等の訪問先や移動先等での迅速かつ正確な業務処理、書類作成、服薬履歴管理等の各種調剤業務に役立つ仕組みを組み入れ、構築しました。 2.セキリュティシステムで個人情報を完全ガード 三重にガードされたセキリュティシステムにより、個人情報を電子情報ベースで厳格に管理されています。 3.在宅医療チームの共有化ツール クラウドを利用することにより、薬局と薬剤師間のみならず、担当医師やケアスタッフがアクセス可能なデーターベースを構築、医療チーム相互の迅速な情報共有化を可能にしています。 日本調剤では、在宅業務へのハード面の取り組みとして、昨年から東京都内と岩手県盛岡市の2ヵ所に設置した本格的な無菌調剤室を中心として、注射薬の調剤・提供も実施してHIT(Home Infusion Therapy)への取り組みを強化しています。日本調剤では、今後、さらに全国各地で地域における医薬の専門家として患者さまの在宅療養をサポートすべく取り組んでまいります。 記 1. 名称 「日本調剤・在宅コミュニケーションシステム」 2.概要 機能情報端末「iPad」の機能活用による、移動先での在宅業 務で必要とされる情報データーベースへのアクセス、処方入力等の業務支援、医療チーム各位との情報共有化が可能なコミュニケーションシステム 3.運用開始 平成24年春より試験運用による導入開始、7月より本格的に日本調剤の調剤薬局でのシステム利用開始 4.対象店舗 すでに全国50店舗で導入、年度内には70店舗で実施。 5.開発協力 株式会社メディエイド 代表者:杉山博幸、所在地:東京都千代田区九段南4-2-10 電話:03‐5213‐9791 Website http://www.mediaid.co.jp/ 以上
-
日本調剤 東京23区全域を対象に医薬品即日配送の実証実験を開始 オンライン発熱外来受診後の急ぎの需要を検証
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、バイク便の業界最大手である株式会社ソクハイ(東京都品川区、代表取締役社長:木村 章夫、以下「ソクハイ」)の即配サービスを使った医薬品即日配達の実証実験を1月12日より開始する運びとなりました。東京都内の19店舗において体制を整備し、オンライン発熱外来を受診した患者さまを対象に、東京23区全域を配送対象地域として即日配送のニーズを検証します。 日本調剤では、新型コロナウイルスの感染拡大による患者さまへの感染リスクの低減を目指し、オンライン服薬指導に対応する体制を整備してまいりました。新型コロナウイルスやインフルエンザが流行し、発熱によるオンライン診療・服薬指導の非接触の需要が高まる中、より早く患者さまのもとへ医薬品をお届けするため、ソクハイの即配サービスの実証実験を実施いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のための時限的な措置として厚生労働省より発出された通知*1に基づいて電話等による服薬指導を受けた後、当日中の医薬品受け取りを選択いただけます。これにより、急な発熱や体調不良の際にも、ご自宅にいながら当日中に服薬を開始することが可能となります。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、お届け先の玄関前等ご指定の場所にお荷物を置く非対面でのお受け取りもご選択いただけます。 ■実証実験の概要 東京都内即日配送対応19店舗 日本調剤 三田薬局 (東京都港区) 日本調剤 用賀中央薬局 (東京都世田谷区) 日本調剤 竹ノ塚薬局 (東京都足立区) 日本調剤 根津薬局 (東京都文京区) 日本調剤 江東薬局 (東京都江東区) 日本調剤 練馬旭丘薬局 (東京都練馬区) 日本調剤 旗の台薬局 (東京都品川区) 日本調剤 築地薬局 (東京都中央区) 日本調剤 蒲田中央薬局 (東京都大田区) 日本調剤 飯田橋薬局 (東京都千代田区) 日本調剤 八幡山薬局 (東京都杉並区) 日本調剤 亀有薬局 (東京都葛飾区) 日本調剤 葛西薬局 (東京都江戸川区) 日本調剤 鷺ノ宮薬局 (東京都中野区) 日本調剤 学芸大学駅前薬局 (東京都目黒区) 日本調剤 ときわ台薬局 (東京都板橋区) 日本調剤 落合南長崎薬局 (東京都豊島区) 日本調剤 新飯田橋薬局 (東京都新宿区) 日本調剤 幡ヶ谷駅前薬局 (東京都渋谷区) 即日配送可能エリア 東京23区全域 実証期間 2021年1月12日(木)~3月31日(水) 実証内容 オンライン発熱外来受診・オンライン服薬指導実施後の医薬品の即日配送の検証 ■株式会社ソクハイについて ソクハイの概要はこちらをご参照ください。 https://www.sokuhai.co.jp/profile/ 日本調剤は今後も感染症の拡大防止に努めて患者さまが安心して治療・服薬を継続できる体制を整備するとともに、良質な医療サービスの提供を通して社会に貢献してまいります。 以上 *1 新型コロナウイルス感染拡大防止のための時限的な措置として厚生労働省より発出された通知:https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤、『外来がん治療専門薬剤師』暫定取得者が25名に ―薬局所属認定者の約3分の1を占める人数―
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)では、医療環境が変化する中でも患者さまに質の高い医療を提供するため、薬剤師の専門性を高めるさまざまな取り組みを行なっております。その一つとして取得推進を進めている、日本臨床腫瘍薬学会(以下「JASPO」)が定める「外来がん治療専門薬剤師(以下『BPACC』)」の暫定取得者が、2021年9月18日時点で調剤薬局業界の中でトップである25名となったことをご報告いたします。これは薬局に所属するBPACC暫定取得者のうち3人に1人以上が日本調剤グループの薬剤師※1であることを示します。 厚生労働省が掲げる「患者のための薬局ビジョン」により、「対物業務から対人業務」への転換が進む中、高度薬学管理への対応が求められています。日本調剤は創業当初から”医療人”としての薬剤師教育に注力しており、質の高い薬剤師を育成する多彩な教育制度を展開しています。教育専任スタッフを中心にきめ細やかなフォロー体制を構築し、基礎・専門共に一人ひとりに合わせたスキルアップをサポートしています。 その中で近年特に当社が注力しているのが、がん治療に対応できる薬剤師の育成です。現在のがん治療は外来が主流になりつつあり、院外でも安心して薬物治療を続けられるよう、高度なスキルと専門知識を持った薬局薬剤師が必要とされています。その専門性を有した薬剤師の指標の一つであるのが、JASPOが認定する「BPACC」です。 2021年現在、暫定認定を取得するためには「外来がん治療認定薬剤師(以下『APACC』)」の取得者であること、また5年以上の実務経験があることが条件となっています。日本調剤では以前よりAPACC取得希望者を集めた強化チームを結成し、積極的に取得支援を行なってまいりました。その結果、2021年9月18日時点で、APACCの上位資格であるBPACCを25名が暫定取得し、薬局所属の暫定取得者72名※1のうち3分の1以上を占めております。 暫定認定の取得者は、JASPO主催のがん診療病院連携研修を修了することで本認定を取得できます※2。日本調剤では今後もがん診療病院連携研修への参加を含め、認定取得を目指す薬剤師が円滑に準備を進められるような環境整備に力を入れてまいります。 また強化チームではそのほか、資格取得に必要な症例報告のサポートや、申請にかかる費用の補助など、資格取得を支援するための仕組みも整えています。また、2019年度からは薬剤師のさらなるモチベーション向上とスキルアップを後押しするため、外来がん治療認定薬剤師を含む特定の外部認定資格を持つ社員に対し、一定額の手当を支給する人事制度を導入しています。 当社では、高い専門性を持つ薬剤師が職能を存分に発揮できる環境を整え、同時にスキルアップを目指す薬剤師の研鑽を積極的にサポートすることで、地域医療に貢献してまいります。 ※1 「外来がん治療専門薬剤師 暫定認定者名簿 2021年9月18日現在承認」より当社にて集計 ※2 2022年以降申請開始 以上 【JASPO「外来がん治療専門薬剤師」制度について】 外来がん治療を安全に行うための知識とスキルを持ち、がん患者さまとそのご家族をサポートできる薬剤師を養成するために創設された制度です。従来の「外来がん治療認定薬剤師」認定制度に加え、さらに専門医療機関と薬局が連携し、的確ながん治療を提供できると認められた薬剤師が認定を受けることができます。 詳細についてはJASPOの公式サイトをご参照ください。 https://jaspo-oncology.org/senmon/ 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し3,000名超の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
【JPニュースレター】「2022年度日本調剤グループ学術大会全国大会」「JP-CSアワード2022ロールプレイ大賞本選」を開催
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、さる9月11日(日)、質の高い薬局スタッフの養成を目的とした「2022年度日本調剤グループ学術大会全国大会」および「JP-CSアワード2022ロールプレイ大賞本選」をパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて同時開催いたしました。学術大会は6度目、ロールプレイ大賞は5度目の開催となります。本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、来場者を制限した状態での現地開催と、オンライン開催を併用したハイブリッド形式で行い、全国から合わせて約500名の社員が聴講しました。 ■急速に変化する時代において、薬局が提供できる価値を追求 「2022年度日本調剤グループ学術大会全国大会」 より多くの職員に学術発表の機会を提供するため、2016年に始まった日本調剤の社内学術大会。日常業務の中で見出した疑問を出発点に数多くの職員が研究発表に挑戦し、知見を共有する機会として、年に1度開催されています。 新型コロナウイルス感染症の影響で2020年はやむなく中止、2021年は完全オンライン形式での実施という対応になっておりましたが、今年、十分な感染予防対策を取ったうえで3年ぶりの現地開催が実現しました。 薬局認定制度、オンライン活用の推進など新たな取り組みが次々に始まり、薬剤師・薬局に求められる役割や、薬物治療も多様化する時代。それに合わせて、回を重ねるごとに発表者の職種、研究内容も多様化が進んできました。 今年度の大会テーマは、「『頼られる価値を創り出す』~エポックメイキングへの挑戦~」です。一般講演では、全国8ブロックでの予選会から選出された全23演題を「高度薬学・がん関連セッション」「薬局業務・地域連携セッション」の2会場に分け、口頭発表と質疑を行いました。登壇者の中には新卒2年目の社員も含まれ、若手・ベテラン問わずグループ全体でノウハウの共有と専門性の向上をはかりました。 一般講演のほか、薬剤師育成や教育を主なテーマとする基調講演と特別講演も執り行われました。 基調講演はシンポジウムの形をとり、小児科領域の薬物治療に関する高い専門性を持った薬剤師を育成するための課題について、日本薬剤師研修センターが認定する小児薬物療法認定薬剤師の資格を持った社員の経験談を交えながらディスカッションを行いました。 また特別講演では当社FINDAT事業部部長・上田 彩が登壇し、「医療における意思決定に必要な医薬品情報」をテーマに講演を行いました。2024年度に改訂される、新たな薬学教育モデル・コア・カリキュラムの内容に触れながら、チーム医療の中で薬剤師の職能をさらに発揮し、質の高い薬物治療を提供するために、エビデンスに基づいた医薬品情報の重要性が高まっていることについて解説しました。 *新たなモデル・コア・カリキュラムに対する「FINDAT」を用いた支援の取り組みにつきましては、併せてこちらのニュースリリースもご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20220901_nr2/ ■目の前の患者さまのニーズを聴き出し、最も適した応対を目指す 「JP-CSアワード2022ロールプレイ大賞本選」 当社では創業以来、薬局スタッフの患者さま応対力の向上に力を入れており、2008年からは毎年、社内表彰制度「JP-CSアワード」を開催しています。「JP-CSアワード」には、患者さま満足度アンケートをもとに質の高いサービスを提供している店舗および店舗スタッフをたたえる「店舗表彰(BPB)」と「個人表彰(BSH)」を設けておりますが、2017年からは舞台上で模擬患者さまを相手に接客ロールプレイを披露する「ロールプレイ大賞」を加え、3本立ての表彰を行っています。 今年は全国の予選会を勝ち抜いた18名が「薬剤師・登録販売者部門」「オペレーター・管理栄養士部門」に分かれてその応対スキルを競い合いました。 ロールプレイ大賞では、舞台上に薬局店内を再現し、制限時間7分の中で、患者さまのご来局からOTC医薬品・化粧品・サプリメントの販売、健康相談、お見送りまでのロールプレイを行います。 会場、そして配信用カメラの先にも大勢の観客がいるという普段とは大きく違う環境に、出場者たちの顔には緊張の色が浮かんでいましたが、同じ店舗で働くスタッフからの応援ビデオメッセージが流れると、少しだけ表情が和らいだ様子に。日頃の業務で培った接遇スキルを存分に発揮していました。 本大会のテーマである「絆を深める、未来につながる~専門知識を持った医療コンシェルジュ~」に準じ、OTC医薬品・健康食品の提案に限らず、食事指導や運動指導なども含め幅広い選択肢の中から最も目の前の患者さまに適した提案ができているかに着目して審査を行いました。すでに日本調剤が強みとして有している「温かいあいさつ・きっかけ作り、正確さ・誠実さ、気配り・心配り」に加え、患者さま一人ひとりに向き合い、頼りにされるために必要である「聴き出し力」「提案力」「患者さま情報活用力」の要素が応対の中にバランスよく含まれているかが主な評価項目となりました。 ■優秀な発表を表彰 すべての演題・ロールプレイ終了後、審査員による厳正なる審査に加え、「オーディエンス賞」選出のため聴講者全員参加による投票を行いました。 学術大会では各部門「社長賞」と「オーディエンス賞」1名ずつ、ロールプレイ大賞では各部門「最優秀賞」「優秀賞」1名ずつに加え全出場者の中から「オーディエンス賞」1名が選出されました。 日本調剤では、薬局スタッフが互いに専門性を磨き合い、さらなるレベルアップを図るとともに、今後の地域医療に貢献できる人材育成に注力していきます。 <日本調剤グループについて> https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 <日本調剤株式会社について> https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。 <JP Newsletterについて> 本ニュースレターは、日本調剤の薬局や薬局で働く薬剤師・医療事務・管理栄養士のことを皆さまにご理解いただくために、随時、発行しています。超高齢社会を迎え、地域における医療の重要性が高まる中、身近な医療提供・健康管理の場である調剤薬局、そして薬や栄養などの専門知識を持った薬剤師・管理栄養士は、地域における医療・健康管理の重要な担い手として期待されています。
-
大学病院と研修制度で連携!大学病院実務研修制度を本格導入
調剤薬局が大学病院と研修制度で連携! 薬剤師教育制度の充実で地域医療に貢献を 全都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(所在地:東京都千代田区、代表者:取締役社長三津原博)では、従来の薬剤師教育制度に加えて、地域医療に貢献できる薬剤師の育成を目的として、本年度、旭川医科大学病院(北海道旭川市)において実施した大学病院実務研修制度を、来年度から全国の大学病院に拡大し、本格導入いたします。 日本調剤では創業以来、薬剤師教育に注力し、15ステップアップ研修、サブリーダー研修、管理薬剤師研修など、レベルや職務に応じた独自の教育制度を作り実施することで薬剤師の能力やモラルの向上に努めてきました。今後、地域包括ケアシステムの構築や在宅医療の推進を背景にこれからの薬剤師に求められる役割を果たすため、大学病院での実務研修制度を通じて薬剤師教育の範囲を広げていきます。 本年度、先行事例として、旭川医科大学病院にて当社の薬剤師が研修を実施しました。 ■研修概要 研修期間 (1)平成26年10月6日から平成26年11月14日 (2)平成27年2月9日から平成27年3月20日 研修人数 (1)・(2)各2名 研修時間 (1)各144時間 (2)各152時間 主な研修内容 (1)・(2)ともに調剤室業務、注射剤室業務、混注業務、製剤室業務、DI業務 病棟業務、薬務室業務、定例会参加など薬剤部業務全般 来年度は以下の大学病院にて当社の薬剤師による研修を予定しています。 ■平成27年度研修検討病院 北海道エリア(1施設*) 関西エリア(2施設) 東北エリア(1施設) 中国・四国エリア(2施設) 関東・甲信越エリア(2施設) 九州・沖縄エリア(2施設) 東海・北陸エリア(2施設) *旭川医科大学病院にて継続研修予定 以上 <ご参考> ◆日本調剤の薬剤師教育制度の概要 日本調剤は、薬剤師教育を薬局運営における最優先課題と捉え、全国の各支店に教育情報部を設置しています。専任の教育スタッフが「薬学知識」「店舗管理知識」「理念教育」の3つを柱に薬剤師のスキルアップのために積極的に活動しています。 継続的な研修である15ステップアップ研修や各種勉強会、ビデオ学習、薬歴評価などに加え、経験年数や職務に応じたフォローアップ研修、サブリーダー研修、管理薬剤師研修によって2,000名以上の薬剤師一人ひとりにとって必要な研修を実施します。 今回、大学病院実務研修が加わることで、従来の教育制度では十分でなかった病院での各種業務を習得し、広範囲にわたる薬剤業務を身につけることで、在宅医療や地域医療へのさらなる貢献が期待されます。 ◆大学病院における研修の様子 (旭川医科大学病院)
-
高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」 標準フォーミュラリーの対象薬効群を拡充し本契約を開始
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、2020年6月1日~9月30日の期間限定で、無料モニター向けに公開していた、本邦初*1の“高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」”(https://www.findat.jp)の本契約を2020年10月1日より開始し、標準フォーミュラリーの対象薬効群を拡充することをお知らせいたします。 2020年6月1日~9月30日に実施した「FINDAT」の無料モニター期間では、大学病院をはじめとした約130の医療機関からお申込みいただきました。また、モニター利用者にアンケートを行った結果、「標準フォーミュラリー」および「薬効群比較レビュー」について、85%の方にご満足いただいています*2。 本契約開始にあたり、主要コンテンツである標準フォーミュラリーは「フィブラート系薬」・「MR拮抗薬」・「抗ヒスタミン薬」・「ACE阻害薬・ARB」・「PPI・P-CAB」・「高尿酸血症・痛風治療薬」・「抗インフルエンザウイルス薬」・「NK1受容体拮抗型制吐薬」・「5-HT3拮抗型制吐薬」・「ビスホスホネート系薬」の計10の薬効群を掲載し、10月15日には「過活動膀胱治療薬」・「NSAIDs」・「速効型・超速効型インスリン」の3薬効群を追加予定です。また、2020年度中に、「ESA製剤」・「高リン血症治療剤」・「神経因性疼痛治療薬」・「G-CSF製剤」の標準フォーミュラリー、薬効群比較レビューを作成予定です。 新薬評価は、臨床上で影響の大きい新薬を評価し、製造販売承認後4~5ヶ月で掲載いたします。医療機関での医薬品採用時の検討資料として、薬事委員会等にてご活用いただけます。 日本調剤では、「FINDAT」の導入を通じて、DI業務の負担を軽減し「対物業務から対人業務」への転換やチーム医療の充実、フォーミュラリーの作成をサポートし、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために全力で注力してまいります。 *1:2020年5月25日時点、日本調剤調べ*2:第2回モニターアンケート結果(集計期間:2020年9月7日~11日、回答数:40/92施設、満足・やや満足と回答した割合) ■サービス概要 ・名称: FINDAT (呼称:ファインダット) ・形態: 医薬品情報のWEB配信サービス ・URL: https://www.findat.jp ・推奨閲覧端末: PC ・動作環境(ブラウザ): Google Chrome(最新版)、Microsoft Edge(最新版) ・提供可能施設: 病院(順次、診療所や調剤薬局へも拡大予定) ・料金: お問合せください ・お申込み・お問合せ:FINDAT(https://www.findat.jp)トップページのお問合せフォームより、ご連絡ください。 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインや二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”の造語です。現在、商標登録出願中です。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT (https://www.findat.jp)トップページのお問合せフォームより、ご連絡ください。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp
-
【JPニュースレター】日本薬学会等で学術発表 調剤薬局の取り組みを発信!
日本調剤の学術発表レポート 日本薬学会等で調剤薬局の取り組みを発信! 全都道府県で調剤薬局を展開している日本調剤株式会社(本社:東京都千代田区、代表者:取締役社長 三津原博)では、調剤薬局における医療の実践や、多くの患者さまと接することで得られる貴重な情報により、大学や学会、医療機関とも連携しながら調査・研究を進め、学術発表を積極的に行っています。今回はさる3月に参加しました社外発表事例をご紹介します。 《3月25日~28日 日本薬学会 第135年会》 「薬学が拓く、健康と未来」をテーマとして開催された、日本薬学会第135年会(3月25日~28日、兵庫県神戸市)では、4演題をポスター発表しました。 ◆発表テーマ①:南関東におけるインフルエンザ感染パターンと「A型/B型」の流行との関係~薬局データを用いた検討~ 発表内容:インフルエンザの流行パターンがA型/B型など型ごとの流行に影響を受けることについて、薬歴データを分析して明らかにしました。代表発表者:当社教育情報部 福岡勝志 (帝京平成大、ヘルスヴィジランス研との共同発表) ◆発表テーマ②:長期処方患者に対する薬局薬剤師の積極的な関与~患者登録10例を1年間追跡した経験からの報告~ 発表内容:長期処方患者を対象に非来局時に薬剤師が介入することによって、様々な問題を解決し適正な薬物治療を継続できるか検討しました。代表発表者:日本調剤辰野薬局 小澤夕佳 (日本アプライド・セラピューティクス学会、明治薬大と共同発表) ◆発表テーマ③:お薬手帳の利用実態とニーズ 発表内容:お薬手帳の利用実態とニーズについて、2014年度の患者さま満足度アンケートを集計・分析して明らかにしました。 代表発表者:当社教育情報部 井原綾子 ◆発表テーマ④:検査値処方せんの現状と今後の期待 発表内容:検査値が記載された院外処方せんが増えつつある中、業務に及ぼす影響や今後薬剤師が果たすべき役割を探るべく調査を行いました。 代表発表者:当社教育情報部 中居利恵 《3月22日 BIファーマシストアワード2015 奨励賞受賞!》 「薬剤師が実践する患者中心の医療」をテーマとした日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社が主催する同賞において、当社発表が応募のあった35題の中から最終選考10題に選ばれました。3月22日(日)東京国際フォーラム(東京都千代田区)にて開催された最終選考会において奨励賞に選ばれました。 発表テーマ:長期処方患者に対する薬局薬剤師の積極的な関与 発表者:日本調剤辰野薬局 管理薬剤師 小澤夕佳 《3月14日~15日 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2015》 「花開く5つの和 がんチーム医療の実践」をテーマに開催された日本臨床腫瘍薬学会学術大会2015(3月14日~15日 みやこめっせ、京都市勧業館)において、日本調剤 柏の葉公園薬局 管理薬剤師 宮川知久がポスター発表を行いました。 発表テーマ:病院と保険薬局の合同勉強会の効果検証~薬局薬剤師の意識に及ぼす影響~ 発表者:日本調剤柏の葉公園薬局 管理薬剤師 宮川知久 当社では、今後も地域の中で求められる調剤薬局の役割を果たし、その存在意義を高めるべく、薬局現場で得られた知見やデータを積極的に発信していきたいと考えております。また、研究成果に基づく薬局現場における実践により、その成果を地域社会や患者さまへ還元してまいります。 ●日本調剤の学術発表 (https://www.nicho.co.jp/corporate/business/academic/) 以上 本ニュースレターは、下記よりPDFファイルにてご覧いただくことができます。 平成27年4月13日付【JPニュースレター】日本調剤の学術発表レポート 日本薬学会等で調剤薬局の取り組みを発信!
-
日本調剤のOTC医薬品シリーズ『5COINS PHARMA』でニキビ治療薬「キルカミンアクネクリーム」を新発売
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、日本調剤のOTC医薬品プライベートブランド『5COINS PHARMA』の新商品として、「キルカミンアクネクリーム」を、2024年4月15日よりヘルスケア通販サイト「日本調剤オンラインストア」(https://store.nicho.co.jp/)において、4月26日より全国の日本調剤の店舗と当社グループ以外の一部薬局様※1において販売いたします。 業界初※2の価格均一OTC医薬品ブランドである『5COINS PHARMA』は、セルフメディケーション推進にあたり、OTC医薬品の価格が一つの課題であるとの考えからブランドの開発に着手しました。品質と有効成分量にこだわった上で、原則税込550円※3というお手頃価格を実現しております。また、薬剤師・登録販売者が、商品選びや購入後のフォローを実施しているため、安心してご使用いただけます。 このたび、繰り返す大人ニキビを根本から治療する「キルカミンアクネクリーム」が新たにラインアップに加わりました。 ■「キルカミンアクネクリーム」 3つの特長 1.ニキビの炎症を抑えるイブプロフェンピコノールを配合 抗炎症作用のあるイブプロフェンピコノールがニキビや吹き出物の炎症を鎮めます。 2.イソプロピルメチルフェノールがアクネ菌を殺菌 殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールが、ニキビの原因の一つであるアクネ菌の増殖を防ぎ、イブプロフェンピコノールとともに、ニキビを根本から治療します。 3. 透明に変化するクリームで外出時も目立ちにくい クリームはお肌に塗ると、色が白から透明に変化するため、外出時にも目立ちにくいです。 日本調剤では、『5COINS PHARMA』の販売・流通を通じて、セルフメディケーションのさらなる推進と、皆さまの日々の健康サポートに貢献してまいります。 ※1 日本調剤では医薬品卸売販売業の許可を取得しています※2 当社調べ(2022年5月実施。約30社のプライベートブランドやナショナルブランドを対象に、「OTC均一価格ブランド」「一般用医薬品均一価格ブランド」として調査)※3 『5COINS PHARMA』シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます ■商品概要 商品名称 キルカミンアクネクリーム リスク分類第2類医薬品 薬効分類 化膿性疾患用薬 希望小売価格 550円(税込) 【日本調剤オンラインストアでのご購入はこちらから】 https://store.nicho.co.jp/products/OS202403270001?sku=4535653002966 ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
本邦初*1 内航船上でのオンライン診療・オンライン服薬指導を実施 ~船上でもいつもと変わらぬ医療提供体制を整備し、船員の健康管理を支援~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、株式会社ゼクト(東京都千代田区神田、以下「ゼクト」)、公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院(東京都千代田区神田駿河台、以下「三楽病院」)と連携し、2022年10月7日に八重川海運株式会社(徳島県阿南市、以下「八重川海運」)の内航船員を対象とした船上でのオンライン診療、オンライン服薬指導までの一気通貫となる本邦初*1の症例を実施いたしました。 〈内航船上でのオンライン診療・オンライン服薬指導実施フロー〉 日常生活や医療などに必要な物資を流通させる内航船員は、社会機能を支えるエッセンシャルワーカーとしてその重要性が再認識されています。一方、陸から離れた船舶という特殊環境下で長期間勤務する船員の平均疾病発生率は0.81%であり、陸上労働者の疾病率の0.41%と比較して高い中*2、内航船員の健康確保の必要性についても焦点が当てられ、2022年4月に施行された「改正船員法」では船舶所有者に労務管理責任者の選任等が義務付けられ、さらに2023年4月には船員の健康確保に向けた新たな制度が導入される予定です。 このような中、日本調剤、ゼクト、三楽病院が協働して慢性疾患を抱える内航船員の治療・服薬をサポートする体制を整備し、八重川海運の内航船員を対象とした初事例を行いました。 <各社コメント> ※順不同 ■日本調剤株式会社 薬剤本部薬剤企画部 次長 馬場 克典 コメント 船上でのオンライン診療・オンライン服薬指導から処方薬をお届けする仕組みが構築できたことで、海上でお薬が不足した場合や処方量の調整が必要になった際にも速やかに対応でき、治療の質やスピードの向上に貢献できると期待しています。長期間の乗船であっても船員の皆さまが安心していただけるよう、今後もサポートを続けてまいります。 ■株式会社ゼクト 代表取締役 世古口 学 氏 コメント 内航海運は、日本の経済・生活を支える物流インフラとして不可欠である一方、船員の高齢化や健康不安、過重労働などの課題にも焦点が当てられています。このたび初事例として構築した本スキームを内航海運業界に広め、日本の経済・生活の一助となれるよう尽力いたします。 ■八重川海運株式会社 代表取締役 村田 泰 氏 コメント 内航船は、日本の物流の約4割、産業基礎物資輸送においては約8割の輸送を担っております。また不審船の通報や災害の多い日本では重要なライフラインでもあります。その担い手である内航船員にも陸上と同等の医療サービスが不可欠であり、当社では本スキームを活用した船員の健康確保が有効だと考えております。 ■公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 外科統括部長 伊藤 契 先生 コメント 長期間にわたって船上という特殊環境下で働く内航船員は、平均疾病発生率も高く、航海中の医療機関の受診も困難なため、継続して治療に専念できる体制が必要不可欠です。船上生活中も顔を見ながら安心して診察を受けていただき、陸上にいるときと同様に治療・服薬を続けられる本スキームに大きな期待を寄せています。 ■「ゼクト・メディカル・オンライン(ZMO)」について https://www.dsp.zect-mc.co.jp/ ゼクト・メディカル・オンライン(ZMO)は在宅医療や離島・へき地などの環境でオンライン診療を提供するシステムです。専用端末により世界No.1クラスのNEC顔認証システムを導入しログイン時の手間を軽減するとともにセキュリティ面でも安心して運用が可能です。 また、オンライン診療中に画像を撮影することも可能となっており、患者さんの病変部位の撮影だけでなく関連する処方箋なども撮影することができます。この機能を用いて撮影した処方箋の画像を医療機関から薬局へ共有することが可能です。 なお、2020年に同システムを用いた海上での電波強度を確認する実証実験を行い、陸地からおよそ40km程度離れた海域でもビデオ通信が可能であることを確認しています。 日本調剤では、日本の物流を支える内航船員の健康確保をサポートすることで、医療と社会に貢献してまいります。 *1 2022年10月7日現在、当社調べ*2 2020年10月23日開催船員部会資料より https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001368618.pdf ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。 【株式会社ゼクトについて】 https://www.zect-mc.co.jp/ 2007年に情報セキュリティに関するコンサルティング業務を主軸として創業し、病院など重要な個人情報を取り扱う施設にて情報セキュリティマネジメントシステムの構築を行ってきました。コンサルティング時の方針として情報は利活用されなければ意味がない、ということを念頭に置き「次世代医療基盤法に基づく 医療情報の利活用のための情報セキュリティ対策ガイド」を発刊しました。 2013年からはシステム開発・販売の事業も開始し、人間ドック・健診施設向け受診者案内支援システム「Medical Dock Navi Z」、内航海運業界における船員の労務管理・健康管理を行う「デジタル船員手帖」を提供しています。 【八重川海運株式会社について】 http://www.yaegawa.co.jp/ 1964年に創業し、徳島県阿南市に本社を構えて海運事業を行っております。日本の基幹産業の国内海上輸送を担う内航船事業、所有船2隻、国際海上輸送を担う外航船事業、所有船9隻、現在合計11隻で海運事業を展開しております。またグループとして船舶管理業、外食事業および小売り事業を展開し、社会に貢献してまいります。
-
日本ジェネリックの一般用医薬品 第2弾 『ロキソプロフェン錠「JG」』を発売
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社のグループ会社である日本ジェネリック株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本ジェネリック」)は、2020年1月24日(金)から同社の一般用医薬品第2弾として『ロキソプロフェン錠「JG」』を発売いたします。全国の日本調剤の店舗または日本調剤のヘルスケア通販サイト「日本調剤オンラインストア」で購入いただけます。 日本ジェネリックは、「優れた医薬品をもっと広く、もっと身近に」を企業理念に掲げ、有効性・安全性、そして経済性に優れたジェネリック医薬品を、調剤薬局事業で培った知識と経験をもとに、患者さまにお届けしております。 現在680品目(※2019年12月末現在)の医療用医薬品を製造販売しておりますが、このたび、一般用医薬品として『ロキソプロフェン錠「JG」』を発売しました。これは当社が2018年12月に発売した『ミノキシジルローション5%「JG」』に続く一般用医薬品第2弾です。 『ロキソプロフェン錠「JG」』は、ロキソプロフェンナトリウム水和物を配合した解熱・鎮痛薬です。白を基調としたシンプルなパッケージデザインを採用し、調剤薬局事業で得た知見をもとに実際のユーザー目線に立った包装設計となっています。 1. 用量をわかりやすく明記 錠剤の包装シートには、錠剤ごとに用量をはっきりと印字しています。ロキソプロフェンは飲み過ぎてしまうと胃に大きなダメージを与えるリスクがあるため、正しい用量をわかりやすく記載しています。 【ロキソプロフェン錠JGの特徴~ユーザー目線で設計したパッケージ~】 2. どちらからも開けられる外箱 包装箱は左右どちらからも開けられるようにミシン目が入っており、廃棄の際に押しつぶしやすくなっています。 同商品は全国の日本調剤の薬局で販売するほか、日本調剤のヘルスケア通販サイト「日本調剤オンラインストア」(URL:https://store.nicho.co.jp)でも販売いたします。どちらも購入に際して、日本調剤の薬剤師が飲み合わせや、気になる症状のご相談いただきます。 日本ジェネリックは、ジェネリック医薬品の普及にまい進し、超高齢社会における医療費適正化に尽力するとともに、患者さま思いの商品・サービスの開発を通して、良質な医療サービスを提供してまいります。 以上 ■商品概要 商品名:ロキソプロフェン錠「JG」 分類:第1類医薬品 発売日:2020年1月24日(金) ※店頭販売開始 規格:12錠(6シート×2) 有効成分:ロキソプロフェンナトリウム水和物68.1㎎(無水物として60㎎)/錠 効能・効果:頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱 用法・用量:症状があらわれた時、成人(15歳以上)が1回 1錠(1日2回まで)をなるべく空腹時をさけて水又はお湯で服用してください。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。(服用間隔は4時間以上おいてください) 希望小売価格:500円(税抜) 発売元:日本ジェネリック株式会社 製造販売元:長生堂製薬株式会社 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。 【日本ジェネリック株式会社について】 http://www.nihon-generic.co.jp/ 2005(平成17)年1月、日本調剤株式会社(東証一部上場)の100%出資により「優れた医薬品をもっと広く、もっと身近に」を企業理念として発足しました。その特長は、日本調剤が培ってきた医療・医薬業界での実績と信頼を礎(いしずえ)として、全国の医薬品卸を介した販路を持っていること。また、医薬品処方の現場における患者さまの生の声や、医療従事者のさまざまなニーズをダイレクトに把握し、それを直接、研究・開発に活かせることなど、他社にはない強みを持っています。日本ジェネリックでは、高品質で安価なジェネリック医薬品を安定的に供給し続けることにより、患者さまの安心や負担軽減のみならず、逼迫(ひっぱく)する国の医療費低減にも貢献すべく“今までにない新しい視点”での製品開発・供給に取り組んでおります。
-
【日本調剤 盛岡中央薬局】県内初の無菌調剤室が完成!
全都道府県で調剤薬局を運営する日本調剤株式会社では、盛岡市で営業する日本調剤 盛岡中央薬局(盛岡市内丸17-8)の一部を改装、岩手県で初となる無菌調剤室(クリーンルーム)を設置しました。 本年7月より在宅で療養する患者さま、特にHIT(Home Infusion Therapy)を必要とする患者さまに対する注射薬の無菌調剤業務を開始いたしました。 超高齢社会の到来により、病院へ入院しての治療から、自宅で治療を続ける"在宅療養"へと移行してきていますが、自宅での療養では、点滴での栄養補給のための高カロリー輸液や医療用オピオイド、抗がん剤等の提供が必要となるケースも少なくなく、薬局での調剤業務においてもクリーンルームでの無菌調剤が必要でした。 無菌調剤とは、自宅で療養されている患者さまに対して、無菌調剤室(クリーンルーム)において、高カロリー輸液や医療用オピオイド注射薬、抗がん剤の調剤を行うものです。 実施するには、クリーンルーム設置への投資コスト、患者さま宅への訪問業務の発生等、薬剤師への注射薬の無菌調剤技能習得等が必要となり、多くの調剤薬局では、まだ在宅向けの調剤業務への取り組みは進んでいない状態です。 こうした状況の中、「医薬分業」を企業理念として掲げる日本調剤では、地域における医薬の専門家として地域医療チームの一員に加わり、今後、さらにニーズが高まる無菌調剤業務への取り組みを積極的に行うこととして、今回、盛岡市内の中心部にあり、当社の旗艦店舗でもある日本調剤 盛岡中央薬局において、同薬局内に岩手県初となる無菌調剤室(クリーンルーム)を設置、HITへ対応できる調剤薬局となりました。 今後、盛岡市を中心に岩手県内周辺地域の在宅医療において、HITに対応できる調剤薬局として岩手県の地域医療に貢献してまいります。 【日本調剤盛岡中央薬局 無菌調剤室設置 概要】 薬局名:日本調剤 盛岡中央薬局(無菌調剤室は3Fに設置) 住所:盛岡市内丸17-8 電話:019-622-1193 設備:無菌調剤室(クリーンルーム)、バイオハザード室(抗がん剤対応)、エアシャワー室、前室など 施設面積:約38㎡ 業務開始:平成23年7月より
-
日本調剤、『外来がん治療専門薬剤師』取得者・暫定取得者が計39名に ―薬局所属認定者の約3分の1を占める人数―
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)では、医療環境が変化する中でも患者さまに質の高い医療を提供するため、薬剤師の専門性を高めるさまざまな取り組みを行なっております。その一つとして取得推進を進めている、日本臨床腫瘍薬学会(以下「JASPO」)が定める「外来がん治療専門薬剤師(以下『BPACC』)」について、取得者が19名、暫定取得者が20名、計39名となったことをご報告いたします。これは薬局に所属するBPACC取得者のうち約3人に1人が日本調剤グループの薬剤師※1であることを示し、調剤薬局業界の中でトップの数字です。 厚生労働省が掲げる「患者のための薬局ビジョン」により、「対物業務から対人業務」への転換が進む中、高度薬学管理への対応が求められています。日本調剤は創業当初から”医療人”としての薬剤師教育に注力しており、質の高い薬剤師を育成する多彩な教育制度を展開してきました。教育専任スタッフを中心にきめ細やかなフォロー体制を構築し、基礎・専門共に一人ひとりに合わせたスキルアップをサポートしています。 中でも近年特に当社が注力しているのが、がん治療に対応できる薬剤師の育成です。 日本人の2人に1人はがんに罹患すると言われる※2現在、がん治療は外来が主流になりつつあり、外来でがん治療を受ける患者さまの数は、入院でがん治療を受ける患者さまの約1.5倍となっています※3。院外でも安心して薬物治療を続けられるよう、高度なスキルと専門知識を持った薬局薬剤師が必要とされています。2021年8月に開始した薬局認定制度においても、がん治療に対する高い専門性を持った薬局が「専門医療機関連携薬局」として認定されるようになり、日本調剤でも全国で37店舗が認定を受けています(2022年6月16日時点)。 その専門性を有した薬剤師の指標の一つであり、専門医療機関連携薬局の要件にも関連しているのが、JASPOが認定する「BPACC」です。 日本調剤ではBPACCと、同じくJASPOが定める「外来がん治療認定薬剤師(以下『APACC』)」※4の取得強化チームを結成し、積極的に支援を行なっております。 その結果、2022年5月20日時点で、BPACCを19名が取得、20名が暫定取得※5となり、薬局所属の取得者118名※1のうち約3分の1を占めております。 日本調剤ではがん診療病院連携研修への参加推奨のほか、資格取得に必要な症例報告のサポートや、申請にかかる費用の補助など、資格取得を支援するための仕組みを整えています。また、2019年度からは薬剤師のさらなるモチベーション向上とスキルアップを後押しするため、外来がん治療専門薬剤師を含む特定の外部認定資格を持つ社員に対し、一定額の手当を支給する人事制度を導入しています。 当社では、高い専門性を持つ薬剤師が職能を存分に発揮できる環境を整え、同時にスキルアップを目指す薬剤師の研鑽を積極的にサポートすることで、医療に貢献してまいります。 ※1 「外来がん治療専門薬剤師認定者名簿 2022年5月」「外来がん治療専門薬剤師暫定認定者名簿2022年6月」より当社にて集計※2 国立がん研究センター 最新がん統計より※3 厚生労働省 平成29年患者調査より※4 BPACCはAPACCの上位資格※5 暫定認定の取得者はJASPO主催のがん診療病院連携研修を修了することで本認定を取得可能 以上 【JASPO「外来がん治療専門薬剤師」制度について】 外来がん治療を安全に行うための知識とスキルを持ち、がん患者さまとそのご家族をサポートできる薬剤師を養成するために創設された制度です。従来の「外来がん治療認定薬剤師」認定制度に加え、さらに専門医療機関と薬局が連携し、的確ながん治療を提供できると認められた薬剤師が認定を受けることができます。 詳細についてはJASPOの公式サイトをご参照ください。 https://jaspo-oncology.org/senmon/ ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
【JPニュースレター】「2021年度日本調剤グループ学術大会全国大会」 「JP-CSアワード2021ロールプレイ大賞本選」をオンライン開催
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、さる9月12日(日)、質の高い薬局スタッフの養成を目的とした「2021年度日本調剤グループ学術大会全国大会」および「JP-CSアワード2021ロールプレイ大賞本選」をオンラインにて同時開催いたしました。学術大会は5度目、ロールプレイ大賞は4度目の開催となります。本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、初めてWeb会議システムを活用することで開催を実現し、全国から500名以上の社員が聴講しました。 ■それぞれの立場で専門性を高めることを目指して 「2021年度日本調剤グループ学術大会全国大会」 より多くの薬剤師に学術発表の機会を提供するため、2016年に初めて開催された日本調剤の社内学術大会。その後、調剤薬局業界のリーディングカンパニーとして当社の学術活動を社外の方々にも広く知っていただくため、公開形式へ変更となり、発表者の職種、研究内容も多様化が進みました。 2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず中止となったものの、今年度はオンライン開催という形で、日本調剤グループ社員が共有すべき学術的な情報を発表する場が再び設けられました。 今年度の大会テーマは、「新時代に必要とされる薬局~『真の医薬分業の実現』に向けて~」。時代とともに変遷する薬局業界の中で、患者さまから選ばれるために研鑽する薬局職員の様子が垣間見える発表が多く集まりました。一般講演では、全国8ブロックでの予選会から選出された全22演題を「高度薬学・がん関連セッション」「薬局業務・地域連携セッション」の2会場に分け、グループ全体でノウハウの共有と専門性の向上をはかりました。 一般講演のほか、薬剤師育成や研究計画の立案方法をテーマとする基調講演・教育講演も執り行われました。基調講演はシンポジウムの形をとり、がんに関する高い専門性を持った薬剤師を育成するための戦略や課題について、実際に外来がん治療認定薬剤師の資格を持った社員の経験を交えながらディスカッションを行いました。 また特別講演として、当社FINDAT事業部部長・上田 彩から、「FINDATの日本調剤店舗トライアルのご報告」と題し、薬局におけるFINDAT活用の可能性についての提案もありました。 *「FINDAT」の薬局展開の取り組みにつきましては、併せてこちらのニュースリリースもご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20210407_nr1/ ■患者さまに頼りにされる”医療コンシェルジュ”へ 「JP-CSアワード2021ロールプレイ大賞本選」 当社では創業以来、薬局スタッフの患者さま応対力の向上に力を入れており、2008年からは毎年、社内表彰制度「JP-CSアワード」を開催しています。「JP-CSアワード」には、患者さま満足度アンケートをもとに質の高いサービスを提供している店舗および店舗スタッフをたたえる「店舗表彰(BPB)」と「個人表彰(BSH)」を設けておりますが、2017年からは舞台上で模擬患者さまを相手に接客ロールプレイを披露する「ロールプレイ大賞」を加え、3本立ての表彰を行っています。 例年のロールプレイ大賞では舞台上に薬局店内を再現して接客ロールプレイを行なっていましたが、今回は出場者・患者さま役・審査員をWeb会議システムでつなぎ、対面での応対を想定したロールプレイを実施しました。7分間の制限時間の中でお迎えから健康相談(服薬補助、食事指導、運動指導、OTC商品の販売など)、お見送りまでの一連の応対を再現します。 全国の予選会を勝ち抜いた16名(※うち1名都合により欠場)が「薬剤師・登録販売者部門」「医療事務・管理栄養士部門」に分かれ、日頃の業務で培った応対スキルを存分に発揮しました。 審査では、本大会のテーマである「地域とつながる、未来につながる~パーソナルな応対ができる医療従事者へ~」に順じた要素が評価対象となりました。すでに日本調剤が強みとして有している「温かいあいさつ・きっかけ作り、正確さ・誠実さ、気配り・心配り」に加え、患者さま一人ひとりに向き合い、頼りにされるために必要である「聴き出し力」「提案力」「患者さま情報活用力」の要素が応対の中にバランスよく含まれているかを評価しました。 ■優秀な発表を表彰 すべての演題・ロールプレイ終了後、審査員による厳正なる審査の上、両大会の表彰式を執り行いました。今年はオンライン開催の利点を生かし、Web聴講者の投票で決定される「オーディエンス賞」がそれぞれの大会で設けられました。 学術大会では各部門「社長賞」と「オーディエンス賞」1名ずつ、ロールプレイ大賞では各部門「最優秀賞」「優秀賞」1名ずつに加え全出場者の中から「オーディエンス賞」1名が選出されました。 日本調剤では、薬局スタッフが互いに専門性を磨き合い、さらなるレベルアップを図るとともに、今後の地域医療に貢献できる人材育成に注力していきます。 <日本調剤株式会社について> https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し3,000名超の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。 <JP Newsletterについて> 本ニュースレターは、日本調剤の薬局や薬局で働く薬剤師・医療事務・管理栄養士のことを皆さまにご理解いただくために、随時、発行しています。超高齢社会を迎え、地域における医療の重要性が高まる中、身近な医療提供・健康管理の場である調剤薬局、そして薬や栄養などの専門知識を持った薬剤師・管理栄養士は、地域における医療・健康管理の重要な担い手として期待されています。
-
多彩な教育プログラム
日本調剤では、薬剤師一人ひとりが、患者さまの生命・健康を守る医療人として、高い志、高度な専門知識・技能を取得するための教育プログラムを設けています。研修制度 e-Learningシステムを利用した実践的かつ総合的なプログラムで、日本調剤の薬剤師教育の最大の柱です。15のステップからなり、ステップアップテストに合格することで上位のランクに昇級し、段階的に一通りの学習を進めていくことができます。 全国どこでもオンラインで学習およびテストを行うことができ、学習・確認を繰り返しながら複合的な知識を身につけていきます。また、各薬剤師の進捗状況はシステムにより把握することができます。 15ステップアップ研修 薬剤師教育システムとして定評のある15ステップアップ研修は、「JPラーニング」として外部に販売しており、研修認定薬剤師の単位申請にも対応しています。 WEB教育システム「JPラーニング」 イントラネットを活用した教育関連情報サイトです。過去のものから最新のものまで1,200件以上の資料を集約し、薬学関連情報から患者さま満足向上のための学習ツールまで、日々の業務に関わる情報を網羅的に配信しています。サイト内では、業務の中で出てきた疑問を教育専任スタッフに質問できる「質疑応答システム」や勉強会資料を動画配信する「ビデオライブラリ」など、いつでもすぐに確認できる体制を整備しています。 また、社員同士の意見交換の場として「過誤防止の取組み」「CS特派員の部屋」「在宅ブログ」なども活発に利用されています。 教育情報部E-classroom薬剤師ステージ制度「JP-STAR」 薬剤師の知識・スキル面における専門性を評価・推進する、日本調剤独自の社内制度です。高度薬学管理を行なう薬剤師と、健康サポート薬局を担う地域に寄りそえる薬剤師を、長期育成していくことを目的としています。そのステージアップの要件のひとつとして、社外認定取得も視野に入れた5領域(がん、緩和ケア、認知症、糖尿病、腎臓病)を中心とした独自の社内認定制度があります。 在宅医療の現場に対応できる薬剤師を養成するため、全国で在宅医療集合研修を実施しています。おもに「フィジカルアセスメント」や「経腸経管栄養」、「在宅中心静脈栄養法(HPN)」等をテーマに講義・実習を行っており、在宅医療についての実践的な知識・技能を学べるようになっています。 在宅医療集合研修 地域包括ケアシステムの構築や在宅医療の推進を背景に、チーム医療の中で活躍できる薬剤師の育成を目指して、全国の大学病院を中心に研修を導入しています。 研修では、注射調剤業務や混注業務、DI業務、病棟業務など、病院での研修ならではの経験を積むことができ、今後求められる薬剤師のスキルを磨くことができます。 また、病院薬剤師を対象とした「薬局実務研修」も実施し、相互理解を深めることでさらなる連携強化に努めています。 病院実務研修 日本調剤ではCS(患者さま満足度)向上のため、接遇マナーやコミュニケーションスキルを学ぶ研修を継続的に行っています。薬局での患者さまとの応対に活用するため、ロールプレイングを多く取り入れた内容になっています。 心に寄り添う医療接遇研修(スナッグル研修) JP-CSアワードとは、年に一度実施される患者さま満足度アンケートの集計結果をもとに、薬局サービスに優れた店舗・個人を表彰する制度です。薬局でのCS向上を目的に、2008年から毎年実施しています。 この取り組みは、リクナビNEXT主催の「第2回 グッド・アクション」において、現場活性化部門を受賞しました。表彰制度が従業員のモチベーションの向上につながっており、かつ企業として仕組み化している点が評価されました。 JP-CSアワード社内表彰制度「JP-CSアワード」が「グッド・アクション」で受賞! 健康サポート薬局研修 日本調剤では、厚生労働省が指定する確認機関(日本薬学会)より、健康サポート薬局研修実施機関の承認を他機関と協同で受け、研修を実施しています。 処方解析・服薬指導勉強会 服薬指導のレべルアップを目的に、教育専任スタッフによる勉強会を開催しています。「病態と治療」をテーマに、 管理職から新入社員まで幅広い受講者を対象としています。 薬歴評価 薬剤師の資質向上のためにも日本調剤は薬歴を重要視しており、 独自の評価システムを構築し、評価および必要に応じて指導を行っています。 また、「薬剤服用歴記載の手引き」や「かかりつけ薬剤師の手引き」などの資料も用意しています。 社外ジョブチャレンジ制度 社外ジョブチャレンジ制度とは、日本調剤の社員として病院へ派遣され勤務(※)する制度です。産休・育休による欠員等での人員不足に課題を抱える病院薬剤部の課題解決の一環として、2018 年から新たにスタートしました。産休・育休代替業務が終了した後には、病院で得た知識や経験を薬局現場で生かしていけるため、薬剤師としてさらにレベルアップできます。 ※ 派遣法及びその施行令等によって認められている業務
-
日本調剤グループ、さらなる組織パフォーマンスの向上と人的資本経営の推進を目指し、本社を新オフィスに移転
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)を中心とした日本調剤グループは、東京本社オフィスを2024年9月に東京都港区芝に移転(予定)することになりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 ■オフィス移転の背景 日本調剤グループは2007年から現在の地に本社を構えてまいりましたが、近年のコロナ禍を越えるとともに、従業員の年齢、性別、働き方も多様化してきております。そのような時代や会社を取り巻く環境の変化、オフィスの魅力や従業員の働きがいに対応するなど、人的資本経営が企業の重要経営課題となるなか、本社機能を移転することに検討を重ねてまいりました。 ■新オフィスの概要 新本社所在地 東京都港区芝五丁目33-11田町タワー アクセス JR田町駅より徒歩2分、地下鉄三田駅より地下2階で直結 業務開始予定日 2024年9月予定 新オフィスのワークスペースは、メンバー同士・部署間・グループ会社間でのコミュニケーションがとりやすいよう、シームレスな空間作りにこだわっています。異なる価値観やバックボーンを持ったメンバー同士が様々な意見やアイデアを出し合い、コミュニケーションを活性化させ、事業成長と組織パフォーマンスを最大化していけるために、気軽なミーティングや休憩ができるスペースを拡充しています。また、田町タワーには、働き方が多様化するなかで「職場で働く価値」を生み出すための設備・施設が取り入れられており、その一つとして緑豊かなオフィステナント専用ラウンジが用意されております。当ラウンジは、イベントスペースとしても貸切可能なコミュニケーションを誘発する癒しとくつろぎのオープンエリアだけではなく、個室ブースや会議室も用意されており、「職場に来たくなる」空間を提供しています。 写真のラウンジは入居テナント専用の共用スペースです。来場者すべてが利用できるわけではないこと、予めご了承ください。 ■最新のBCP対策 非常用発電(地上階設置、オイル・中圧ガス2台の発電機により、共用部の主要設備、専有部内のコンセント・照明用に9日間の電力供給ができるようになっています。また新しい制振構造(免振+制振のハイブリッド構造)により、高い制振性能を持つ建物となっております。 ■環境対応 太陽光発電の設置などの自然エネルギー利用、敷地緑化や屋上・壁面緑化などでのヒートアイランド対策、雨水・雑排水・厨房排水・空調ドレン水の再利用などでCO2削減を始めとした最新の環境対策設備を揃えており、当社のサステナビリティ経営にも寄与しております。 日本調剤グループは新しい東京本社オフィスに移転することで、さらなる組織パフォーマンスの向上と人的資本経営の推進を目指し、すべてのステークホルダーに向き合う姿勢を明確にしてまいります。 ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 日本調剤株式会社 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。 日本ジェネリック株式会社 https://www.nihon-generic.co.jp/ 2005年に発足し、高品質で安価なジェネリック医薬品を安定的に供給し続ける医薬品製造販売事業を担っています。日本調剤が培ってきた医療・医薬業界での実績と信頼を礎(いしずえ)として、医薬品処方の現場における患者さまの声や医療従事者の多様なニーズを研究・開発に生かせることなど、他社にはない強みを生かし持続可能な社会保障制度にも貢献してまいります。 株式会社メディカルリソース https://www.medical-res.co.jp/ 2000年に、医療人材の不足、ミスマッチの課題解決に向け日本調剤ファルマスタッフ株式会社として発足。2008年、株式会社メディカルリソースに社名変更し、医療従事者派遣・紹介事業を担っています。薬剤師・医師・看護師・コメディカルの方々と、医療機関・薬局・企業等へ「多種多様な医療人材の紹介・派遣」、「働き方改革など社会情勢にマッチした人材サービスの相談」で貢献してまいります。 株式会社日本医薬総合研究所 https://www.jpmedri.co.jp/ 2012年に発足し、日本調剤グループの保有する貴重な情報資源を最大限活用した情報提供・コンサルティング事業を担っています。日本調剤が保有する匿名化した年間1400万枚を超える豊富な処方箋情報から、処方動向の解析や、患者さまのアドヒアランス(服薬管理)向上への活用を行っています。また、製薬企業や自治体、関係団体に向けて、医薬品に関する調査・研究、コンサルティングのサポートや、日本調剤の約700店舗の薬局ネットワークを活かした広告プロモーションも行っています。
-
日本調剤、メドレーが提供する調剤薬局窓口支援システム「Pharms」の全店舗*導入を決定 ~患者さまの利便性向上のため、オンライン服薬指導の対応体制を強化~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、株式会社メドレー(本社所在地:東京都港区、代表取締役医師:豊田 剛一郎、代表取締役社長:瀧口 浩平、以下「メドレー」)が提供する調剤薬局窓口支援システム「Pharms(ファームス)」を日本調剤グループの全ての薬局*へ導入することをお知らせいたします。 ■日本調剤株式会社コメント 日本調剤では、オンライン服薬指導が実施可能となった2020年9月1日に合わせてオンライン服薬指導システム「日本調剤 オンライン薬局サービス」を自社開発し、全国の当社グループが運営する薬局店舗でのオンライン服薬指導の体制を構築してまいりました。昨今の医療分野におけるデジタル活用の規制改革が進む中、一気通貫のオンライン診療・オンライン服薬指導の体制整備によるさらなる患者さまの利便性向上のため、全店舗*に「Pharms」を導入することを決定いたしました。今後は「日本調剤 オンライン薬局サービス」と「Pharms」の2つのシステムを活用することで患者さまの薬物治療をサポートします。 また、コロナ禍における感染症の拡大防止の観点からも、これらのシステムを活用することで非対面・非接触での服薬指導およびお薬のお受け取りのニーズに応えます。 日本調剤では、患者さまが安心して治療・服薬を継続できる体制を整備し、医療と社会に貢献してまいります。 * 物販店舗を除く ■調剤薬局窓口支援システム「Pharms」について メドレーが開発・運営を行う「Pharms」は新しい患者体験と業務効率の向上を目指した調剤薬局向けシステムです。患者さまはオンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS(クリニクス)」をダウンロードすることで、診療所・病院でのオンライン診療から調剤薬局でのオンライン服薬指導までを利用することがきます。忙しいビジネスパーソンや子育て中の方、体が不自由な方の負担軽減に繋がるだけではなく、医療機関内での感染防止にも繋がるものです。 調剤薬局窓口支援システム「Pharms(ファームス)」 https://pharms-cloud.com オンライン診療・服薬指導アプリ「CLINICS(クリニクス)」 https://clinics.medley.life/ ■「日本調剤 オンライン薬局サービス」について 詳しくはこちらのプレスリリースをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20200901_nr2/ ■日本調剤株式会社 概要 代 表 代表取締役社長 三津原 庸介 所在地 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー37階 U R L https://www.nicho.co.jp/ ■日本調剤株式会社について 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。 ■ 株式会社メドレーについて メドレーは、エンジニアと医師・医療従事者を含む開発チームを有し、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、インターネットサービスを提供しています。現在、より良い医療・介護の実現に向けて、以下のサービスを展開しています 患者向け「オンライン診療・服薬指導アプリ CLINICS」 https://clinics.medley.life 診療所・病院向け「クラウド診療支援システムCLINICS」 https://clinics-cloud.com 調剤薬局窓口支援システム「Pharms」 https://pharms-cloud.com 医師たちがつくるオンライン医療事典「MEDLEY」 https://medley.life 医療介護の求人サイト「ジョブメドレー」 https://job-medley.com 納得できる老人ホーム探し「介護のほんね」 https://www.kaigonohonne.com ■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL 03-6810-0826 E-mail pr-info@nicho.co.jp 株式会社メドレー 広報グループ TEL 03-4531-5674 E-mail pr@medley.jp
-
医薬品情報WEBプラットフォーム「FINDAT」、日本調剤の薬局440店舗に拡大 活用事例集をとりまとめ、質の高い薬物治療と持続可能な社会保障制度へ貢献
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、2023年4月より医薬品情報WEBプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」を日本調剤が運営する全国の調剤薬局の中から大学病院・総合病院の門前薬局を中心に440店舗に拡大しました。あわせて、日本調剤の「FINDAT」導入薬局でとりまとめた「FINDAT」活用事例集を発行。さまざまな活用事例を当社薬局職員や「FINDAT」導入施設にて共有することで、さらなる活用の進展につなげてまいります。 2021年8月に施行された「地域連携薬局」、「専門医療機関連携薬局」の認定制度において、地域の医療機関と医薬品の適正使用に関する情報提供の連携や、地域の医薬品情報室としての役割が施設基準として求められています。当社では、認定制度が目指す薬局の姿を体現し、患者さまにとって身近な薬物治療の専門家としてより質の高い医療を提供できるよう、2021年4月から医薬品情報WEBプラットフォーム「FINDAT」を当社の一部店舗に先行導入し、薬局での活用方法を検証してまいりました。 このたび、大学病院・総合病院の門前薬局を中心に、「FINDAT」導入店舗を440店舗に拡大しました。また、既に「FINDAT」を導入済みの日本調剤の薬局から集積した特に有益な活用事例36件をまとめ、事例集として発行。トレーシングレポートや在宅訪問時におけるエビデンスと経済性に基づいた処方提案、服薬期間中の患者さまへのテレフォンフォローや副作用モニタリングなど、さまざまなシーンにおける「FINDAT」の活用事例を掲載しています。本事例集を当社薬局職員や「FINDAT」導入施設向けに共有することで、「FINDAT」を活用したより質の高い医療提供を目指します。 日本調剤では、社会や医療環境の変化に伴い調剤薬局・薬剤師の役割が多様化する中、高い専門性を持つ薬剤師が職能を存分に発揮できる環境を整え、患者さまへの質の高い薬物治療の提供と、持続可能な社会保障制度への貢献を目指してまいります。 ■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ 日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。 https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/ 【医薬品情報WEBプラットフォーム「FINDAT」について】 https://info.findat.jp/ 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報WEBプラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
薬剤師生涯教育e-ラーニングシステム『JPLearning』外部受講者向け専用インターネットサイトがスタート
全国規模で調剤薬局チェーンを展開している日本調剤株式会社(代表取締役社長:三津原博、本社:東京都千代田区、東証1部)では、薬剤師生涯教育研修向けe-Learning (イー・ラーニング)システム『JPLearning(ジェー・ピー・ラーニング)』の外部受講者向け専用インターネットサイト(URL https://www.jplearning.jp/)を本年9月25日よりスタート、定評ある薬剤師生涯教育研修システムの外部向けの販売強化を行いました。 日本調剤は、1980年の創業以来、「医薬分業」を企業理念として掲げ、一貫して調剤薬局事業に取り組み、いまや日本を代表する調剤薬局企業として多くの優秀な薬剤師を育成、良質で価値ある医療サービスの提供企業として取り組んでおります。 とくに調剤薬局業務の要である薬剤師教育には、業界屈指の充実した教育研修カリキュラムを実施しており、日本調剤の薬剤師は、営業店舗の9割以上が大病院前という薬局特性に対応して、医療機関から要求されるきわめて高度な処方せん調剤に対応、また薬の効果を最大限発揮できるよう患者さまへの丁寧な服薬指導を行っており、優秀な薬剤師育成の観点からも、業界では「教育の日本調剤」とまで呼ばれる存在となっております。 薬剤師生涯教育研修向けe-ラーニングシステム『JPLearning(ジェー・ピー・ラーニング)』は、全国各地で勤務する薬剤師に対して、日本中、どこで勤務していても、最新薬学知識はもちろん日本調剤で実践されている高度な教育研修カリキュラムが学べるよう、IT(情報技術)の最先端を駆使して構築されたe-ラーニングシステムです。また、現役の薬剤師のみならず、ブランク後に再就職を考えている方や、保険薬局に就職を希望している学生の方などにも最適な学習ツールです。その主な内容は、日本調剤の薬剤師教育の柱とも呼ぶべき"15ステップアップ研修"として体系付け、e-Learningシステムに織り込んだもの。保険薬剤師に必要な知識を網羅した全15ランクからなる一問一答式のe-Learningが基本で、印刷して持ち運び可能なテキストも標準装備しています。各ランクの学習を全て終了すると、認定試験の受講資格が得られ、これに合格していくことにより、上位ランクにステップアップしていきます(パソコン端末から受験可能です)。 この社内e-Learningシステムは、従来『JPLearning』として社外の薬剤師向けに販売しておりましたが、外部からのユーザー数および問い合わせ件数の増加を受け、この度専用ホームページを立ち上げました。 『JPLearning』は317のコンテンツを15のランクに振り分け、一問一答式のクイズで学習を進めますが、補助資料としてテキストも搭載しておりますので、周辺知識も確認することが可能です。また、このテキストは印刷もできますので、パソコンがない場所でも学習することができます。つまり、得意分野はクイズで学習し、不得意分野はテキストとクイズを組み合わせて学習するなど、自分で学習を組み立てて受講することができます。 いろいろと試したものの長続きしなかった方、再就職に不安を感じている方、社員(薬剤師)教育をお考えの企業のご担当者、自己研鑽をお考えの方、来年度から始まる「長期実務実習」に不安を感じている学生の方など、当サイト内にあるお試し版にアクセスしていただき、ご検討ください。 ※(財)日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師制度」の『自己研修』として単位請求が可能です。 単位請求に関しての詳細は、(財)日本薬剤師研修センター(http://www.jpec.or.jp/)の「認定制度・研修案内」を参照ください。 【JPLearning HPアドレス】 https://www.jplearning.jp/ ※トライアル画面(お試し版)がありますのでお試しください。 【同カリキュラムに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 教育情報部 電話:03-6810-0821 またはE-Mail:jpl-info@nicho.co.jp →2016年4月より以下へお問い合わせ先が変更となりました。 株式会社メディカルリソース JPLearning事務局 電話:03-3212-5580 またはE-Mail:jpl-info@nicho.co.jp
-
血糖値の上昇を防ぐ!食事のコツ【栄養だより2019年11月号】
日本調剤の薬局(一部のみ)では、季節に合わせた健康情報をお届けする情報紙として、毎月「栄養だより」を配布しています。ご自身の食事や健康に興味を持ち、生活習慣を見直すきっかけにしてもらいたいという思いから、管理栄養士が健康に関する情報を発信しています。その中から一部内容を編集してご紹介します。 糖尿病リスクの指標となる「血糖値」とは 厚生労働省の調査によると、「糖尿病が強く疑われる人」、「糖尿病の可能性を否定できない人」はどちらも約1,000万人いると推測されています。そもそも糖尿病に関係する血糖値とは一体何なのでしょうか。 エネルギー源となるブドウ糖の濃度を表す「血糖値」 血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度で、ご飯やパン、麺類、果物などに含まれている糖質(炭水化物)を摂ると上昇します。すい臓から分泌される「インスリン」というホルモンの働きにより、血液中のブドウ糖は細胞の中に取り込まれ、日々の活動のエネルギーに利用されます。 血糖値は、食事の量や運動によっても変化しますが、健康な人はインスリンがうまく働くことで一定の範囲内に収まっています。 血糖値が高いとなぜ悪いの? 食べすぎや運動不足などの不健康な生活習慣を続けていると、血糖値が高い状態が続いてしまいます。血液中に糖が多いと、血管の壁が壊れやすくなったり、血管が詰まったりすることがあります。つまり、血糖値が高いと、「糖尿病」をはじめ、網膜症や腎症、神経障害などさまざまな疾患や症状を引き起こす可能性が高くなります。 知っておこう!血糖値に関する数値 空腹時血糖 血液中のブドウ糖濃度を表す数値のことで、空腹時の血糖値の状態を知ることができる。食事の内容や時間によって変動しやすい。空腹時血糖が126mg/dl以上の場合には、受診が必要となる。 HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) 血液中のヘモグロビンのうち、 糖と結合しているもの。直近1~2か月の血糖値の状態を知ることができる。直前の食事に左右されないため、比較的正しい数値を測定できるが、普段の食事にばらつきがあると値が高くなりやすい。HbA1c の値が6.5%以上の場合には、受診が必要。 WHO(世界保健機関)では毎年11月14日を「世界糖尿病デー」と定め、世界各地で糖尿病の予防、治療、療養を喚起する啓発運動を行っています。糖尿病について考え、予防に向けて自身の生活習慣を見直してみましょう! 11月14日は「世界糖尿病デー」食事のひと工夫で防ごう!食後高血糖食後高血糖とは? 食後2時間後の血糖値が140mg/dl以上の状態になることを「食後高血糖」といいます。 食事を摂ると、血糖値は一時的に上昇しますが、健常な方の場合、徐々に正常値(110mg/dl未満)まで戻ります。しかし、インスリンが正常に機能しない場合、血糖値は正常値まで戻りません。食後高血糖は、空腹時血糖値は正常であることから、「隠れ糖尿病」とも言われており、注意が必要です。 ポイントは食事の「バランス」と「順番」 食後高血糖を防ぐためには1日3回の食事を規則正しく摂るようにしましょう。食事の量は腹八分目まで。ゆっくりよく噛んで食べることで、少量でも満腹感が得られやすくなります。 また、「食物繊維(野菜・海藻・きのこ)」→「たんぱく質」→「炭水化物」の順に食べることで、血糖値の上昇が緩やかになります。糖質の多い野菜(かぼちゃ・いも類)は炭水化物と同様、最後に食べるようにしましょう。 食事の基本は「一汁三菜」です。主食である「ご飯」に「汁物」と3つの「菜(おかず)」を組み合わせることで、バランスの良い食事が完成します。 血糖値の上昇を抑える食べ方 野菜・海藻・きのこ・こんにゃくのおかず(食物繊維) 1.副菜 肉・魚・大豆製品・卵のおかず(たんぱく質) 2.主菜 ご飯・パン・麺類(炭水化物) 3.主食 日本調剤の「認定栄養ケア・ステーション」では、地域密着型の栄養ケアの拠点として幅広く手厚いサポートを行っています。疾病に関する食事療法のご相談や献立の考案も承りますのでご相談ください。 【参考文献】 厚生労働省. “平成29年国民健康・栄養調査報告”. https://www.mhlw.go.jp/content/000451755.pdf, 糖尿病治療研究会. “血糖の働きを知り、健康づくりに役立てよう”. 10月8日は、糖をはかる日. https://dm-net.co.jp/10-8/learn/ippan.php, 大正製薬株式会社. “血糖値について知ろう!”. 大正製薬ダイレクトオンラインショップ. https://www.taisho-direct.jp/simages/contents/column/life/kettouchiknow/, オムロンヘルスケア. “vol.89 食後高血糖と隠れ糖尿病”. https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/89.html, 沢井製薬株式会社. “気を付けよう!血糖値と生活習慣”. https://med.sawai.co.jp/file/mate/open/02dfef5e-9b0d-452b-9fd9-be66eb21619c00000000027E7575.pdf, 農林水産省. “日本の食文化としての和食”. http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wasyoku.html, 日本イーライリリー株式会社. “高血糖とは食後高血糖~血糖値パターン~”. 知りたい!糖尿病. https://www.diabetes.co.jp/dac/diabetes/hyperglycemia
-
日本調剤が全面サポート! 日経BPムック「時代は薬女」発刊
日 本 調 剤 の 薬 剤 師 が 全 面 サ ポ ー ト 日経ビジネスアソシエ特別編集 「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女」 薬剤師を目指す学生へ魅力を語るムック発刊! 全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原博)では、日経BP社が発行する日経BPムック「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女(ヤクジョ)」の発行にあたり、実際の薬剤師業務の紹介など全面的なサポートを行いました。本年1月5日より同ムックが発行されましたのでお知らせします。 日経BPムック「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女(ヤクジョ)」は、薬剤師の仕事を、若手ビジネスパーソン向け雑誌である「日経ビジネスアソシエ」編集部が、“仕事のノウハウ情報”という同誌ならではの切り口で企画した、薬剤師業界の入門ガイドとなるムックです。これからの日本の医療を担っていく薬剤師たちの未来を、さまざまなテーマで紹介しています。 同ムックでは、キラキラと働く薬剤師女子にスポットを当て、「時代は薬女」と題しています。女優、モデルそしてキャスターと幅広く活躍する桐谷美玲さんと現役の薬剤師の対談や、各界で活躍する著名人からのメッセージやチーム医療に関わる医療関係者の方々へのインタビュー、調剤薬局や病院・医薬品メーカーや食品メーカー・ドラッグストアで働く薬剤師の座談会、薬局業界の最新トレンドなど、わかりやすくて読み応えのあるコンテンツが満載。薬剤師女子に限らず、これから薬剤師を目指す方にとって参考になる内容となっています。 日本調剤では、同ムックの発行にあたり、調剤薬局企業として全面的なサポートを行いました。調剤薬局の薬剤師業務の取材、当社の現役薬剤師へのインタビュー、調剤薬局専業企業である当社の事業紹介など、実際の薬剤師業務の一端を紹介する場面で登場しています。 以上 【「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女」発行概要】 書籍名:日経BPムック 日経ビジネスアソシエ特別編集 「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女」 発 行:日経BP社 内 容:◆素敵に輝く薬剤師の未来 桐谷美玲さんと現役薬剤師との対談 ◆薬剤師業界の未来を大予測!“薬女の時代”は到来するか!? ◆薬剤師免許を取ったら何になる?薬女のハローワーク ◆社会人として必要なスキルはここで学ぶ!薬女力養成講座 ◆薬剤師国家試験合格への道 など 版 型:A4変形 84ページ 価 格:842円(税込) 発行日:平成28年1月5日 販 売:有名書店、各オンライン書店 または 日経BP書店 http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/247710.html 日経BPムック 「活躍できるリケ女の新条件 時代は薬女」表紙 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っている。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し、約2,500人の薬剤師を有する日本を代表する調剤薬局企業として評価を得るとともに、超高齢社会に必要とされる“調剤薬局の新しい姿”を追い求めて、取り組んでいる。 ●本ニュースリリースは、下記よりPDFファイルにてご覧いただくことができます。 平成28年1月14日付『日本調剤が全面サポート! 日経BPムック「時代は薬女」発刊』
-
日本調剤の薬剤師が感じた「在宅医療」のリアルを一冊の本に。書籍「NOT DOING, BUT BEING 『在宅訪問薬剤師』奮闘記」を発売
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、薬剤師在宅訪問サービスに携わる当社社員が社内向けブログに綴った数々のエピソードをまとめた書籍「NOT DOING, BUT BEING 『在宅訪問薬剤師』奮闘記」(日本調剤株式会社 在宅訪問薬剤師ブログ書籍化プロジェクト 著)を2020年12月21日(月)に幻冬舎メディアコンサルティングより出版いたします。 超高齢社会の到来により、医療機関での入院による治療から、自宅で治療を継続していく”在宅医療”への移行が進む中、日本調剤では2009年から薬剤師の在宅訪問サービスを開始。2011年からは本格的に在宅医療専門部署を設け、小児の患者さまからご高齢の患者さままで、さまざまな年齢層、さまざまな疾患をお持ちの方々に対して、きめ細やかな在宅訪問服薬指導に取り組んでいます。 2012年、まだ業界内でも認知度の低かった在宅医療を専門とする「在宅訪問薬剤師」の日常について、社内での認知・理解促進のため、イントラネット上で社員向けブログ「在宅医療official blog~目指せファーマシストへの道~」をスタート。在宅訪問の現場で生まれる葛藤や仕事を通しての成長、喜びや苦労、患者さまとのやりとりなどが薬剤師本人の飾らない言葉で日々投稿されていきました。 在宅訪問薬剤師の働きぶりを目の当たりにし、いつしか薬剤師のみならず、非薬剤師の社員からも、「在宅訪問薬剤師の仕事を、広く社外の方にも知ってもらいたい」という声が上がるようになりました。残念ながら在宅訪問薬剤師の存在は、世間ではまだほとんど認知されていません。医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどと共に、患者さまの在宅療養をサポートする存在として「在宅訪問薬剤師」がいることを知っていただくことは、療養と介護の渦中にいらっしゃる患者さまとご家族はもちろん、これから先、在宅療養が身近な問題になりうるすべての方への一助になると我々は考えました。そして、約8年分にもおよぶ数々のブログ記事から12のエピソードを厳選し、該当記事を執筆した社員に改めてインタビューを行い、この度書籍として発刊させていただきました。 「NOT DOING, BUT BEING」は、緩和医療の礎を築いたイギリスの医師、デーム・シシリー・ソンダースの言葉と言われています。「何をするでもなく、ただそばにいること」。目の前の患者さまのために何ができるのか日々葛藤しながら、患者さまとご家族の人生にそっと寄り添いたいと願う在宅訪問薬剤師たちの姿にこの言葉を重ね、本書のタイトルといたしました。 それぞれのエピソードの後には知っておくとためになる薬剤師発信の情報を「コラム」として掲載し、実用性も兼ね備えた一冊となっています。 ■内容 はじめに 在宅訪問薬剤師たちの12のストーリー ストーリー(1)「自宅で療養したい」その願いをかなえるために在宅薬剤師ができることとは―― コラム:飲み忘れ、飲み過ぎを防ぐための工夫 ストーリー(2)老老介護を支える存在になりたい 認知症の患者さまに在宅訪問薬剤師ができること コラム:高齢者には飲みにくい薬を飲みやすくする工夫 ストーリー(3)「ご家族にも笑顔になってほしい」介護者の負担を軽減する在宅訪問薬剤師の役割とは コラム:レスパイトケアをスムーズにする「お薬の説明書」 ストーリー(4)「最期は自宅で過ごしたい」をかなえるために 医療人、介護スタッフが連携して過ごした老夫婦との10カ月 コラム:老老介護で起こりがちな薬のトラブルや悩みを薬剤師が解決 ストーリー(5)”ただそこにいること”が何より大切 そばにいることで生まれる絆が患者さまを支える コラム:お薬手帳の重要性。在宅では常備薬の管理も大切 ストーリー(6)「ずっと担当してほしい」と言われて……同じ薬剤師が訪問を続ける意味とは? コラム:より良い生活のために、薬剤師に伝えてほしいこと ストーリー(7)Not Doing, But Being. 何をするでもなく、ただそばにいること コラム:無菌調剤を引き受けてくれる薬剤師の存在 ストーリー(8)最期の望みは人それぞれ ご家族と共に願いをかなえる コラム:薬剤師からアドバイス「退院する前に決めておきたいこと」 ストーリー(9)24時間対応だからこそ実現できることがある 最期の食事ができたのはこの薬を届けられたから コラム:QOLの維持には、タイミングを逃さない与薬が大切 ストーリー(10)短い命を輝かせたい 小児の在宅療養で在宅訪問薬剤師ができることとは―― コラム:増える小児在宅療養。家族の負担を軽減するには ストーリー(11)末期がんの在宅療養 家族の選択を在宅訪問薬剤師が支える コラム:在宅で抗がん剤治療を行えるのは本当? ストーリー(12)穏やかな最期を迎えてほしい 緩和ケアに欠かせないこととは―― コラム:緩和ケアで使用される麻薬、危険はないの? Q&A もっと知りたい「在宅訪問薬剤師」に頼めること おわりに ■著者について ≪日本調剤株式会社 在宅訪問薬剤師ブログ書籍化プロジェクト≫ 2020年発足。 日本調剤株式会社の在宅医療部をはじめ、教育情報部、広報部の社員からなり、2012年から同社の在宅訪問薬剤師が日々の業務を通じて感じたことを執筆してきたブログを書籍化するために結成。 ■書籍概要 タイトル:NOT DOING, BUT BEING 『在宅訪問薬剤師』奮闘記 著者:日本調剤株式会社 在宅訪問薬剤師ブログ書籍化プロジェクト 発行:幻冬舎メディアコンサルティング 発売:幻冬舎 仕様:四六判/並製/162頁 発売日:2020年12月21日 価格:1,200円(税抜き) ISBN:978-4-344-93119-0 商品URL(Amazon):https://www.amazon.co.jp/dp/434493119X/ ※本書籍の内容は、日本調剤の薬剤師が実際に関わった患者さまとのやりとりを元に、ご本人が特定されないよう配慮しております。お名前や年齢、性別なども事実と異なります。 以上 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を行ってまいります。
-
日本調剤 高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」紹介サイトを開設
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、4月1日より、高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT(ファインダット)」紹介サイト(https://info.findat.jp/)を新規開設したことをお知らせいたします。 高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」は、医療機関における医薬品情報の収集・評価を一元管理することで、医薬品情報の標準化と効率化を支援するプラットフォームとして2020年6月1日にサービスを開始して以来、大学病院やDPC病院を中心とした全国の医療機関で導入いただいています。また、「FINDAT」の主要コンテンツである標準フォーミュラリーの対象薬効群も17薬効群*にまで拡充。導入施設での標準薬物治療の推進や医薬品購入費の削減などの効果が期待されるほか、地域フォーミュラリーの作成にご活用いただくことで、地域連携の懸け橋となる事例も創出されています。 今般、より多くの医療従事者の皆さまに「FINDAT」が目指すより良い薬物治療をサポートする新しい医療サービスの姿を知っていただくために、「FINDAT」紹介サイトを開設しました。当サイトでは、主要コンテンツである「標準フォーミュラリー」「薬効群比較レビュー」「新薬評価」などの概要、策定プロセス、資料構成を公開し、中立的な立場で医薬品情報が評価、提供されていることをご紹介しています。また、第三者で構成されるフォーミュラリー検討有識者委員会の様子や、「FINDAT」をご利用いただいているお客さまの声を通じた活用事例の公開も予定しています。 日本調剤では、「FINDAT」の導入を通じて、DI業務の負担を軽減し「対物業務から対人業務」への転換やチーム医療の充実、フォーミュラリーの作成をサポートし、患者さまへ良質な医療サービスを提供するために全力で注力してまいります。 *2021年4月1日現在 【高度DIウェブプラットフォーム「FINDAT」について】 「FINDAT(ファインダット)」は、医療従事者のための医薬品情報プラットフォームです。様々なデータソースや、国内外の各種ガイドラインやグローバルで信頼性の高い有料の二次情報データベースなどから網羅的に収集した医薬品情報を中立的に評価し、ウェブ上でご提供するサービスです。 「FINDAT」とは、“FIND(見つける)”+“ATLAS(地図)”を組み合わせた造語で、「医療の道標になるように」という願いが込められています。※「FINDAT」は日本調剤株式会社の登録商標です。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業との評価を得ています。ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスの提供を進めてまいります。 【本サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】 FINDAT 紹介サイト (https://info.findat.jp/) のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。 【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 日本調剤株式会社 広報部 広報担当 TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510 E-Mail:pr-info@nicho.co.jp
-
SDGsとの関わり
日本調剤グループは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。取り組みの一部をご紹介します。 2015年9月の国連サミット において「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」 が採択されました。アジェンダで掲げられた「持続可能な開発目標(SDGs)」は、2030年を達成期限として、あらゆる国と地域が貧困や不平等、教育、環境などに関する17のゴールと169のターゲット達成を目指すものです。 日本調剤グループは、創業以来、医薬分業の実現に向けて医師と薬剤師が、専門性に基づく明確な役割分担と強固なチームワークをもって、安全で質の高い医療サービスを提供し、また、患者さまの経済的な負担軽減を含む医療費の増加抑制を遂行することが、担うべき社会的責任と捉え邁進してきました。同時に当社グループは、事業展開を医薬品の製造販売や医療従事者の派遣紹介、情報提供・コンサルティングまで広げ、調剤薬局事業を中核として幅広く医療に貢献する会社として成長を遂げています。またあらゆる事業活動において、人権や環境に配慮した取り組みをサプライチェーン全体にわたって展開しています。 当社グループの事業活動は、SDGsの掲げる17のゴールに広くかかわり、なかでも親和性が高いのが、次に挙げる4つのゴールです。事業活動を通して社会の発展に寄与するとともに、適切な情報開示と継続的な評価を行い、SDGsへの貢献を目指してまいります。 すべての人に健康と福祉を あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 日本調剤グループは、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業という当社グループの本業の推進と持続的成長の実現こそが、SDGsのゴール3「すべての人に健康と福祉を」の達成に寄与するものと考えています。 高度医療や地域医療への対応、未病・予防など健康をサポートする拠点の拡充といった「薬局機能」の強化・拡張をはじめ、地域の医療・福祉インフラとして質の高い医療サービスを全国どこでも受けられる店舗展開、ジェネリック医薬品の利用促進や医療ビッグデータの利活用を通じ、医療費の増加抑制に寄与するなど、医療のクオリティとアクセシビリティを高めるための取り組みを推進しています。 加えて、医療現場のニーズに合わせた高品質で安全性の高い「ジェネリック医薬品」を研究開発し、GMPを遵守した管理体制のもとで製造、安定供給に向けた体制を整え、さらに医療人材の派遣・紹介では、地域の医療人材の偏在を解消し、地域で医療が滞りなく提供できる体制づくりに寄与しています。 また、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、世界中に大きな影響を与えました。SDGsのターゲット3.3には「感染症」への対処が明記されています。パンデミックによる危機への対応は当社グループにとっても責務であり、ワクチン接種会場における当社薬剤師の接種協力や、医師や看護師などの医療従事者紹介なども行いました。 ターゲット3.8にある「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」の達成に向け、当社グループのあらゆる事業において、すべての人の健康と福祉へのアプローチに取り組んでまいります。 <関連情報> ●良質な医療サービスを提供する調剤薬局の展開 ●健康づくりをサポートする健康チェックステーション ●ジェネリック医薬品の製造販売 ●医療従事者の派遣・紹介 ●医療ビッグデータの利活用 質の高い教育をみんなに すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 日本においては、2025年には団塊の世代の多くが75歳以上となり、超高齢社会に突入します。医療制度への大きな負担が見込まれ、かかりつけ薬剤師・薬局の拡大をはじめ、在宅医療やオンライン服薬指導が求められるなど、薬局を取り巻く環境は大きく変わります。 地域医療機関との連携はもちろん、専門医療機関との連携による高度医療への対応、患者さまへの良質な医療サービスと医療安全の確保が望まれる中、当社グループの事業の中心となる人材である薬剤師に期待される役割は高度化・多様化しています。 SDGsのターゲット4.3に「質の高い技術教育・職業教育」、4.4に「技術的・職業的スキル」が言及されているように、良質な医療サービスの提供には、スキルの高い人材が欠かせません。そのため、15段階にわたる当社独自の教育カリキュラムの提供や外部認定資格の取得支援、新卒薬剤師へのマンツーマン指導など質の高い教育環境の整備に注力しています。また、医療発展に貢献する調査・研究発表や、医療従事者派遣・紹介事業における求職者への当社教育カリキュラムの提供など、業界全体の教育水準の向上に努めています。 薬剤師以外の従業員に対しても同様に、人材を重要な経営資源であると捉え、従業員の成長を促す評価制度や教育制度を整備し、会社の持続的成長を追求していきます。 <関連情報> ●医療人としての質の高い教育環境 ●地域の医療機関などと連携する「地域連携薬局」 ●専門的な薬学管理を提供する「専門医療機関連携薬局」 ●患者さまの在宅療養を支える在宅医療 働きがいも経済成長も すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する 日本においても働き方改革の推進が叫ばれ、SDGsのゴール8「働きがいも経済成長も」の重要性はますます高まっています。ターゲット8.5には「生産的な雇用」と「働きがいのある人間らしい仕事」が、8.8には「全ての労働者の権利」と「安全・安心な労働環境」が掲げられています。 中長期的な企業価値の向上を考える上で、人材を資本として捉える「人的資本」は欠かすことのできない観点です。会社の成長を支える人材確保に努め、障がい者、高齢者の別なく、すべての人材がそれぞれの価値を発揮し、活躍できる環境づくりを進めます。従業員の7割以上を女性が占める当社グループにとっては女性の活躍推進も重要事項であり、育児短時間勤務制度など仕事と家庭の両立を支援する各種制度・施策を整備しています。この他、適材適所へ医療従事者を派遣・紹介し、雇用機会の創出にも取り組み続けます。 当社グループにおいては、従業員を対象にサーベイを実施し、エンゲージメントの現状把握と向上のための施策検討を行っています。働き方改革に加え、具体的なKPIを定めた健康経営を推進し、残業時間の低減や有給休暇取得の促進、多様な働き方の提供、福利厚生制度の充実など、従業員の安全と健康の増進とともに、やりがいをもって働くことができる職場環境を整備していきます。 また、産業医業務提供事業を全国展開し、メンタルヘルスを含む健康管理を中心とした労働衛生管理を支援することで、企業の健康的な働き方を支えます。 <関連情報> ●当社グループの人材マネジメント ●健康経営宣言とその取り組み 産業と技術革新の基盤をつくろう 強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る 日本調剤グループは創業以来、積極的にICT技術を取り入れてきました。2000年代初頭より行ってきた調剤システムの自社開発をはじめ、お薬手帳の電子化、調剤業務の機械化を推し進めるなど、業界に先駆けた取り組みがあり、当社グループの強みは質の高い人材と医療版DXの融合による既存サービスの進化と新たな医療サービスの創出です。 SDGsのターゲット9.1に、「持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ」の重要性が書かれています。当社グループが開発した調剤システムは、オンライン環境に対応し、厳重なセキュリティ体制を敷いた独自のインフラとして構築されたものです。2014年から運用中の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」は、患者さまの健康管理と時間の有効活用をサポートしています。2020年9月からは「日本調剤 オンライン薬局サービス」の運用を開始し、服薬指導から薬の配送までシームレスに受けられるようになりました。医療を受けるプロセスのオンライン化推進により、患者さまへのスマート医療の提供が可能です。 当社グループは今後も医療のデジタルトランスフォーメーションを推進します。医薬品情報WEBプラットフォームFINDATによる医薬品適正使用の効率化・高度化、デジタルツール導入による多店舗オペレーション改革やオンライン医療の推進など、デジタルを活用した新たな顧客体験の創出と新規ビジネスの創出に取り組んでいきます。 これらはゴール8のターゲット8.2「多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性」にも寄与すると考えています。 <関連情報> ●当社グループのDX戦略 ●ICTを活用した医療サービスの提供 ●当社グループ独自の電子お薬手帳 ●医薬品情報WEBプラットフォームFINDAT
-
用語集
日本調剤をよりよくご理解いただくために、医薬業界の専門用語をわかりやすくご紹介しています。 あ行 医薬分業 患者さまの診察、薬剤の処方を医師が行い、医師の発行する処方箋に基づいて、経営的に独立した存在である薬剤師が調剤や薬歴管理、服薬指導を行うという形でそれぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度。 オンライン服薬指導(新設) パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器を用いて、薬剤師が患者さまに服薬指導をすること。これまで対面での服薬指導が義務付けられていたが、薬機法改正により、2020年9月から一定の要件下において、オンライン服薬指導が全国で解禁となった。 2020年4月~2022年3月 点数 薬剤服用歴管理指導料4:43点、月1回まで 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 オンライン診療により処方箋が交付された患者さま 原則3カ月以内に対面で服薬指導を行った患者さま ①服薬指導計画を作成し、計画に基づき実施 ②オンライン服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者 ③お薬手帳により薬の服用歴や服用中の医薬品について確認 在宅患者訪問薬剤管理指導料:57点、月1回まで 在宅患者オンライン服薬指導料 訪問診療の実施による処方箋が交付された患者さま 在宅医療のための訪問を月に1回行っている患者さま ①薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1~3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる ②服薬指導計画を作成し、計画に基づき実施 ③オンライン服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者 ④訪問診療を行った医師に対して、情報提供を文書で行うこと か行 かかりつけ薬剤師 2016年4月に行われた調剤報酬改定に伴い、かかりつけ薬剤師制度が開始された。これは、国が定める一定の要件をクリアした薬剤師の中から、患者さまが希望の薬剤師を1名のみ 指名し同意書に署名を行うことで、担当薬剤師が継続して薬の説明や相談を行う制度であり、かかりつけ薬剤師になるためには、事前に地方厚生局への届出が必要。薬剤師が服薬情報を一元的に把握 担当薬剤師が、他の医療機関・薬局で受け取った薬、市販薬、健康食品、サプリメント等をまとめて把握。重複や相互作用について確認し、薬の服用や避ける必要のある食べ物なども含めて注意点等のアドバイスを行う。 体調変化の確認や薬の残薬調整 担当薬剤師が、過去の服薬記録や副作用歴等も含めて、服用後の薬の効果や体調変化についても継続的に確認を行う。必要に応じて医療機関への疑義照会や副作用・服薬状況のフィードバックを行う。また、多数の残薬が発生している場合は、 次回の処方日数の調整を実施するなど服用薬の整理も行う。 夜間・休日の対応や相談 担当薬剤師は、患者さまの服薬状況や体調変化を継続して把握することで、薬の適正使用や健康維持に関する相談等に対応。緊急の場合には、携帯電話による夜間・休日の対応を実施。 基準 1. 保険薬剤師として3年以上の薬局経験があること 2. 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること 3. 当該保険薬局に1年以上在籍していること 4. 薬剤師認定制度認証機構の研修認定を取得 5. 医療に係る地域活動の取り組みに参画 6. パーテーションで仕切られた独立したカウンター(2020年4月より追加) かかりつけ薬剤師指導料 患者さまが指名した薬剤師(かかりつけ薬剤師)が患者さまの服薬情報を一元的・継続的に把握したうえで服薬指導を行った際に算定される指導料。 2018年4月~2020年3月 点数 :73点 薬局経験3年、在籍1年、週32時間以上勤務 研修認定薬剤師の資格取得 医療に係る地域活動の取り組みに参画 2020年4月~2022年3月 点数:76点 薬局経験3年、在籍1年、週32時間以上勤務 研修認定薬剤師の資格取得 医療に係る地域活動の取り組みに参画 パーテーションで仕切られた独立したカウンター かかりつけ薬剤師・薬局 「患者のための薬局ビジョン」では、かかりつけ薬剤師・薬局に求められる3つの機能について説明されているが、かかりつけ薬局には施設基準等がなく届出は不要。かかりつけ薬剤 師・薬局に求められる仕事は対人業務が中心であり、主な業務は基本料1以外の薬局が地域支援体制加算を算定するのに必要な9項目。厚生労働省は2025年までにすべての薬局を かかりつけ薬剤師・薬局へ再編することを目標としている。 患者のための薬局ビジョン 厚生労働省が2015年10月に発表した指針。これは、地域包括ケアシステムの中で、薬局が服薬情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応を含む薬学的管理・指導などの機能を 果たし、地域で暮らす患者さま本位の医薬分業の実現に取り組むための指針であり、今後の調剤薬局が進むべき方向性と求められる機能が示されている。 出典:厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」 健康サポート薬局 かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局。 保健所へ事前の届出が必要。厚生労働省は2025年までに、 健康サポート薬局を1万から1万5,000件まで登録することを目標としている。 基準 地域包括ケアシステムの中で、医療機関や介護事業者など他職種と連携 健康サポート薬局に係る研修を修了し、5年以上の実務経験を有する薬剤師の常駐 個人情報に配慮した相談窓口 薬局の外側と内側における「健康サポート薬局」の表示 要指導医薬品等、介護用品等の取り扱い 健康チェックステーション 日本調剤の薬局店舗内に併設された、健康相談や健康度測定ができる専用スペースであり、予防や未病に取り組むことで、地域住民の健康をサポートする機能を持つ。 ※「健康チェックステーション」は日本調剤株式会社の登録商標。 後発医薬品・ジェネリック医薬品 医薬品の有効成分そのものに対する特許(物質特許)期間の終了後、他の製薬会社が同じ有効成分で製造・供給する医薬品。法令等では後発医薬品と称されるが、当社グループでは ジェネリック医薬品と呼んでいる。「ジェネリック」とは「一般名」の英語genericによる。 後発医薬品調剤体制加算 後発医薬品を積極的に調剤する薬局を対象に調剤基本料に 加算される報酬。後発医薬品の一層の使用促進を図るため改 定のたびに算定基準が引き上げられてきている。 2018年4月~2020年3月 2020年4月~2022年3月 後発医薬品調剤体制加算1 75%以上:18点 75%以上:15点 後発医薬品調剤体制加算2 80%以上:22点 80%以上:22点 後発医薬品調剤体制加算3 85%以上:26点 85%以上:28点 2018年4月~2020年3月 後発医薬品の調剤数量割合が20%以下の場合は、調剤基本料を2点減算 2020年4月~2022年3月 後発医薬品の調剤数量割合が40%以下の場合は、調剤基本料を2点減算 さ行 在宅医療 体が不自由などの理由で通院が困難である患者さまのご自宅に薬剤師が訪問し、お薬の説明から服薬状況の把握・管理を行い、医師や看護師など多職種と連携して医療を行うこと。 敷地内薬局 2016年10月に薬局と医療機関の構造的な独立性に関する規制が緩和されたことに伴い、病院の敷地内に薬局の出店が可能となった。最も病院との連携が可能であり、高度医療への 対応が求められる。一方、調剤基本料が門前薬局よりも低く設定されている。 自動薬剤ピッキング装置・全自動PTPシート払出装置 日本では、患者さまが服用する薬はPTPシートに封入されていることが一般的である。薬局では人によるPTPシートのピッキング業務が行われている。2つの機械は、カセットにPTPシートを収納しており、処方データを送信することにより必要数のPTPシートを取り揃える機械として普及が始まっている。 診療報酬改定 わが国では、保険診療の対価としての報酬は厚生労働省によって「診療報酬点数表」として医科、歯科、調剤それぞれに定められている。また薬剤の価格は「薬価基準」として定められている。診療報酬は、2年に1度の改定が行われる。 た行 地域支援体制加算 かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日等の地域支援の実績等を踏まえた評価として2018年4月の診療報酬改定に伴い新設。 2018年4月~2020年3月:35点 地域支援体制加算 基本料1の場合 以下を全て満たすこと ①麻薬小売業者の免許 ②在宅医療 年1回以上 ③かかりつけ薬剤師の届出・ 管理薬剤師は薬局経験5年、在籍1年、週32時間以上勤務 基本料1以外の場合 1年に常勤薬剤師1人当たり、以下全ての実績を追加 ①夜間休日の対応実績 400回 ②麻薬指導管理加算の実績 10回 ③重複投与・相互作用等防止加算等の実績 40回 ④かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回 ⑤外来服薬支援料の実績 12回 ⑥服用薬剤調整支援料の実績 1回 ⑦単一建物診療患者さまが1人の在宅薬剤管理の実績 12回 ⑧服薬情報等提供料の実績 60回 2020年4月~2022年3月:38点 基本料1の場合 以下①~③を全て満たし、④⑤のどちらかを満たすこと ①麻薬小売業者の免許 ②在宅医療 年12回以上 ③かかりつけ薬剤師の届出 ④服薬情報等提供料の実績 年12回以上 ⑤地域の他職種連携会議への出席 年1回以上 ・管理薬剤師は薬局経験5年、在籍1年、週32時間以上勤務 基本料1以外の場合 以下①~⑨のうち、8つを満たすこと (①~⑧:常勤薬剤師1人当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間回数) ①夜間休日の対応実績 400回 ②麻薬の調剤実績 10回 ③重複投与・相互作用等防止加算等の実績 40回 ④かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回 ⑤外来服薬支援料の実績 12回 ⑥服用薬剤調整支援料の実績 1回 ⑦単一建物診療患者さまが1人の在宅薬剤管理の実績 12回 ⑧服薬情報等提供料の実績 60回 ⑨地域の他職種連携会議への出席 年1回以上 調剤基本料 薬剤師が処方箋受付1回につき「薬局で調剤を行うこと」に対して支払われる報酬。その薬局がかかりつけ機能を果たしているか、特定医療機関の発行する処方箋応需の集中度、チェーン薬局であるか、などにより点数に差がある。 2020年度改定(変更点は太字で表示) 処方箋受付回数 処方箋集中率 点数 調剤基本料1 調剤基本料2、3、および特別調剤基本料以外 42点 調剤基本料2 月2,000回超~4,000回 85%超 26点 月4,000回超 70%超 月1,800回超~2,000回(追加) 95%超 特定の医療機関から月4,000回超 - 調剤基本料3-イ 同一グループで月35,000回超~40,000回(追加) 95%超 21点 同一グループで月40,000回超~400,000回 85%超 調剤基本料3-ロ 同一グループで月400,000回超 16点 2018年度改定 2020年度改定 要件 処方箋集中率 点数 要件 処方箋集中率 点数 特別調剤基本料 病院と不動産取引 その他の特別な関係95%超 11点 医療機関(診療所を含む)と不動産取引 その他の特別な関係70%超 9点 2018年度改定 かかりつけ機能に係る基本的な業務が年10回未満は調剤基本料を50%減 2020年度改定 かかりつけ機能に係る基本的な業務が年100回未満は調剤基本料を50%減 調剤報酬改定 診療報酬改定のうち、調剤にかかわる報酬改定を指す。調剤報酬は、2年に1度の改定が行われる。 調剤料 薬の調剤に対する点数(費用)のこと。処方日数によって点数が決まっている。 処方日数 1~7 8~14 15~21 22~30 31~ 2018年4月~2020年3月 5点/日(平均27点) 4点/日(平均61点) 67点 78点 86点 2020年4月~2022年3月 28点 55点 64点 77点 86点 電子お薬手帳 処方された薬の情報・記録を一元的に管理し、薬の飲み合わせによる副作用や重複を避けるための手帳アプリ。スマートフォンなどで記録ができる。当社では電子お薬手帳「お薬手帳 プラス」アプリを自社開発している。複数の会社が独自の製品を展開しているが、日本薬剤師会が提供する相互閲覧サービスに参加している会社の製品は他社の製品であっても情報の相互閲覧が可能。 は行 ハイブリッド型薬局 駅前や商店街等に出店し、特定の医療機関の処方箋に限らず比較的広い地域からの処方箋を応需する面対応薬局と、複数の医療機関が集まった医療モールに入居し、それぞれの医療 機関から処方箋を応需するMC型(Medical Center型)薬局 の両方の機能を兼ね備えた薬局。 ※ハイブリッド型薬局は日本調剤株式会社が使用している薬局タイプ名 派遣法 正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。派遣で働く方の権利を守るために、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールが定められている法律。派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間が定められるなど、法律の改正が行われている。 フォーミュラリー 医薬品の有効性・安全性など科学的根拠と経済性を総合的に評価して、医療機関や地域ごとに策定する医薬品の使用指針のこと。良質で低価格な医薬品の使用指針に基づいて、標準薬 物治療を推進することを目的としている。地域フォーミュラリーの普及が進むことで、ジェネリック医薬品の使用が促進され、医療費の増加抑制が期待されている。欧米諸国ではすでに導入されており、日本でも一部で導入され始めている。 ま行 門前薬局 病院の付近にあり、主としてその病院の処方箋を応需する調剤薬局。ただし正式な定義は存在しない。多くの医療機関の処方箋を応需したり、在宅医療に参画したりするなど、かかりつけ薬剤師・ 薬局としての機能を果たすものもある。 や行 薬価改定 保険診療の中で使用される薬品の価格は、「薬価基準」として公定価格が定められている。新薬については年に4回、後発医薬品については年に2回の「薬価基準収載」が行われ、保険診療に使用できることになる。2年に1度、医療機関、薬局への市場流通価格の調査(薬価調査)に基づく薬価改定が行われている。2019年10月には、消費税が8%から10%に引き上げられると同時に薬価改定が実施された。2020年4月からは毎年薬価改定が実施される予定。 薬剤服用歴管理指導料 薬剤師が患者さまに安全にお薬を使用していただくために必要な情報の収集・分析・管理・記録や、お薬のお渡しの際の説明に対して与えられる報酬(点数)のこと。 2018年4月~2020年3月 調剤基本料 1 調剤基本料 1以外 2020年4月~2022年3月 調剤基本料 1 調剤基本料 1以外 6カ月以内の再来局 お薬手帳あり 41点 53点 3カ月以内の再来局 お薬手帳あり 43点 お薬手帳なし 53点 お薬手帳なし 57点 6カ月以内の再来局でない お薬手帳あり/なし 3カ月以内の再来局でない お薬手帳あり/なし 薬機法一部改正 2019年3月19日に薬機法改正案が国会に提出され、2019 年11月27日に可決・成立しました。2020年9月より段階的に施行されることが決定しています。薬局に関する動きとしては、 2020年9月から、オンライン服薬指導が広く実施されます。これまでは、国家戦略特区のみで許可されていた遠隔服薬指導とは別に、ビデオ通話によるオンライン診療を行った処方箋が対象であり対象地域は全国へ広がります。また、糖尿病の重症化予防や慢性頭痛など、対象となる疾患も拡大しています。 また、2021年8月からは薬機法により薬局の機能が定められ、都道府県知事の許可により、看板等へ機能別の表示が可能になります。これにより、患者さまが自分に適した薬局を選択できるようになります。 地域連携薬局 入退院時や在宅医療に他の医療機関と連携して対応できる薬局 ■ プライバシーに配慮した構造設備(パーテーションなど) ■ 入院時の持参薬情報の医療機関への提供 ■ 医師、看護師、ケアマネジャー等との打ち合わせ(退院時カンファレンス等)への参加 ■ 福祉、介護等を含む地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置 ■ 夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参画 ■ 麻薬調剤、無菌調剤を含む在宅医療に必要な薬剤の調剤 ■ 在宅への訪問 専門医療機関連携薬局 がん等の専門的な薬学管理に他の医療機関と連携して対応できる薬局 ■ プライバシーに配慮した構造設備(パーテーション、個室その他相談ができるスペース) ■ 入院時の持参薬情報の医療機関への提供 ■ 医師、看護師、ケアマネジャー等との打ち合わせ (退院時カンファレンス等)への参加 ■ 専門医療機関の医師、薬剤師等との治療方針等の共有 ■ 専門医療機関等との合同研修の実施 ■ 患者さまが利用する地域連携薬局等との服薬情報の共有 ■ 学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置 出典:厚生労働省提出資料(2019年5月)より当社作成 英数字 GMP Good Manufacturing Practiceの略。適正製造基準。アメリカ食品医薬品局が、1938年に連邦食品・医薬品・化粧品法に基づいて定めた医薬品等の製造品質管理基準。各国がこれに準ずる基準を設けており、日本においては、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働大臣が定めた、医薬品等の品質管理基準をいう。
-
【JPニュースレター】日本調剤、「職業体験EXPO 2023」に初出展 ~ 参加した子どもたちの約4割が「薬剤師になりたい」と回答! ~
全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)は、7月29日(土)に開催された小中学生のための新しいカタチの職業体験イベント「職業体験EXPO 2023」(主催:職業体験EXPO実行委員会/株式会社バリューズフュージョン)に出展いたしました。日本調剤の出展ブースでは、『ドキドキ薬剤師体験!薬局の仕事を知ろう。』をテーマとし、薬局・薬剤師のお仕事内容やお薬などについて楽しみながら学べるクイズと、子どもたち自身がご家族の「かかりつけ薬剤師」となって調剤や服薬指導にチャレンジする体験コンテンツを行いました。 ■楽しく学ぼう!薬剤師ってどんなお仕事?お薬の飲み方って? 薬剤師体験にチャレンジする前に薬剤師という職業理解を助け、お薬の正しい飲み方について知っていただくために、全4問のクイズを行いました。参加した子どもたちには3色のカラーボードをお渡しし、クイズの正解だと思う色を上げていただきました。 「全問正解した!」と保護者の方へ笑顔を向ける子や、「お薬を飲むときはコップ一杯のお水がいいんだ!」と学びを得ている子などさまざまな反応が見られました。 ■患者さまに「お薬が飲みづらい」と言われたらどうする?ドキドキ薬剤師体験! クイズの後は、保護者の方の「かかりつけ薬剤師」となって、調剤と服薬指導にチャレンジしていただきました。「錠剤が大きくて飲みづらい……」とおっしゃる患者さま役の保護者の方に対し、子どもたちは医師への確認の元、錠剤を粉砕して粉薬にする提案をします。その後、子どもたち自ら錠剤に見立てたラムネを粉砕。最後に、保護者の方へお薬の飲み方を説明する(服薬指導)というロールプレイ形式の体験を行いました。 参加した子どもたちからは「お薬の粉砕やお薬の飲み方を説明する体験は難しかったけど楽しかった」という声が多く寄せられました。 また、夏休みの自由研究のためにスタッフとして参加していた薬剤師にインタビューする子がいらっしゃったり、保護者の方からは「普段から錠剤を自身で砕いて飲んでいたが薬剤師に相談した方がいいのか」というご相談もいただくなど、親子そろって楽しみながら学んでいただけるイベントとなりました。 ■薬剤師体験後アンケートでは「薬剤師になりたい」との回答が約4割、7割超の子どもたちが薬剤師へ興味 ※アンケート対象:薬剤師体験に参加した小学生の子ども77名(男子15名、女子61名、無回答1名) 薬剤師体験後に、子どもたちにアンケートに回答いただきました。アンケートにご協力いただいた子どもたちの85.7%から、クイズと体験を通じて薬剤師の仕事やお薬の飲み方についての理解が深まったとの回答をいただきました。また、39.0%の子どもたちからは薬剤師に「なりたい」との回答をいただき、「興味があるのでもっと知りたい」との回答と合わせると、76.7%の子どもたちが薬剤師という仕事への興味を示していました。 ≪体験後に寄せられた子どもたちの声≫(一部抜粋) 日本調剤では医療サービス提供企業として、次世代を担う子どもたちの学びを支援するとともに、今後も健康に関する情報提供・啓発活動に積極的に取り組んでまいります。 ■職業体験EXPO2023公式サイト: https://shokugyotaiken.com/event/200 【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/ 日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。 【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/ 1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。 <JP Newsletterについて> 本ニュースレターは、日本調剤の薬局や薬局で働く薬剤師・医療事務・管理栄養士のことを皆さまにご理解いただくために、随時、発行しています。超高齢社会を迎え、地域における医療の重要性が高まる中、身近な医療提供・健康管理の場である調剤薬局、そして薬や栄養などの専門知識を持った薬剤師・管理栄養士は、地域における医療・健康管理の重要な担い手として期待されています。